帯状疱疹予防接種について
令和7年度より帯状疱疹予防接種の公費助成がはじまります!
帯状疱疹とは
帯状疱疹とは、水痘帯状疱疹ウイルスに初感染(いわゆるみずぼうそう)後、生涯にわたって神経に潜伏感染しているウイルスが、加齢、疲労、免疫抑制状態などの免疫力低下によって再活性化して起こる病気です。
主な症状は、体の左右どちらかに帯状に、痛みを伴う水疱の出現です。
合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。
予防接種の対象者
- 年度内に65歳を迎える方
- 60~64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり日常生活がほとんど不可能な方。
- 令和7年度から令和11年度までの5年間の経過措置として、その年度内に70、75、80、85、90、95、100歳(※)となる方が対象となります。
※100歳以上の方については、令和7年度に限り全員対象となります。
| 令和7年度年齢 | 生年月日 |
| 65歳 | 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生の方 |
| 70歳 | 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生の方 |
| 75歳 | 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生の方 |
| 80歳 | 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生の方 |
| 85歳 | 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生の方 |
| 90歳 | 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日生の方 |
| 95歳 | 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日生の方 |
| 100歳 | 大正14年4月2日~大正15年4月1日生の方 |
※100歳以上の方(令和7年度に限る)
(注意)宜野湾市では1と3の対象者の方に個別で案内を送っています。2の該当の有無はかかりつけ医師などにご相談ください。
接種に必要な持ち物
- 予診票
- 健康保険証
※不活化(組換え)ワクチンを受けた方へは、1回目の接種から2か月以上経過後に2回目の予診票をお送りします。案内が届いてから、2回目の接種を受けましょう。
・生活保護受給中の方は、生活保護受給者証または生活保護受給者証明書等の生活保護受給者であることがわかるものを医療機関の窓口に提示してください。
・対象者2.の方は、身体障害者手帳の写しまたは医師の診断書を提示してください。
自己負担額
生ワクチン:4,000円 (1回接種)
不活化ワクチン:11,000円 (2回接種)
指定医療機関
- 宜野湾市内医療機関一覧
- 中部地区
那覇市、浦添市、南部地区、北部地区に関しては現在調整中です。
使用するワクチンの種類と特徴
帯状疱疹ワクチンには生ワクチン、不活化ワクチン(組み換えワクチン)の2種類があり、いずれか1種類を接種します。
各ワクチンは接種回数や接種方法、接種スケジュール、接種条件、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっています。接種をご希望される方は、記載内容を参考にして医師とも相談の上、接種するワクチンをご検討ください。
| 生ワクチン |
不活化(組換え)ワクチン |
|
| 接種方法 | 皮下に接種 | 筋肉内に接種 |
| 接種回数と間隔 | 1回 | 2回(2か月以上の間隔をあける)※ |
| 接種条件 |
病気や治療によって、免疫の低下している方は接種できません |
免疫の状態に関わらず接種可能 |
※病気や治療により、免疫の機能が低下したまたは低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月までに短縮できます。
| 接種後の年数 | 生ワクチン | 不活化(組換え)ワクチン |
| 接種後1年時点 | 6割程度の予防効果 | 9割以上の予防効果 |
| 接種後5年時点 | 4割程度の予防効果 | 9割程度の予防効果 |
| 接種後10年時点 | ー | 7割程度の予防効果 |
いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。
合併症の一つである、帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で、生ワクチンは6割程度、不活化(組換え)ワクチンは9割以上と報告されています。
ワクチンの安全性
ワクチン接種後に以下のような副反応がみられることがあります。
頻度は不明ですが、生ワクチンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、不活化(組換え)ワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。
| 主な副反応の発現割合 | 生ワクチン | 不活化(組換え)ワクチン |
| 70%以上 | ー | 疼痛* |
| 30%以上 | 発赤* | 発赤*、筋肉痛、疲労 |
| 10%以上 |
そう痒感*、熱感*、腫脹*、疼痛*、硬結* |
頭痛、腫脹*、悪寒、発熱、胃腸症状 |
| 1%以上 | 発疹、倦怠感 | そう痒感*、倦怠感、その他の疼痛 |
*:ワクチンを接種した部位の症状
他のワクチンとの同時接種・接種間隔
いずれの帯状疱疹ワクチンについても、医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン等の他のワクチンと同時接種が可能です。
ただし、生ワクチンについては、他の生ワクチンと27日以上の間隔をおいて接種してください。
接種を受けることができない方
- 接種を受ける医療機関で測定した体温が、37度5分以上ある方
- 重い病気にかかっていることが、明らかな方
- 帯状疱疹予防接種により、アナフィラキシー(30分以内に起こる重いアレルギー反応)を起こしたことが明らかな方
- その他、医師により不適当な状態と判断された方
接種を受けるにあたり医師と相談する必要のある方
- 心臓病、腎臓病、肝臓病、血液等の病気がある方
- これまでに、予防接種を接種した後2日以内に熱が出たり、全身の発疹等のアレルギーを疑う病状が現れたことのある方
- 過去に免疫不全の診断がされている方や近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
- 帯状疱疹ワクチン(生ワクチン、不活化ワクチン)の成分にたいしてアレルギーを起こすおそれのある方
- 過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたことのある方
- 生ワクチンの接種を希望される場合、輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方は治療後3か月以上、大量ガンマグロブリン両方を受けた方は、治療後6か月以上おいて接種してください。
- 不活化(組換え)ワクチンの接種を希望される場合、筋肉内に接種するため、血小板減少症や凝固障害を有する方、抗凝固療法を実施されている方
予防接種健康被害救済制度について
予防接種により健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
予防接種では、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、不可避的に生ずるものですので、救済制度が設けられています。
定期接種でない場合(任意接種の場合)には、予防接種健康被害救済制度ではなく、医薬品副作用被害救済制度の対象となります。申請に必要となる手続きなどについては、医薬品医療機器総合機構(PMDA)にご相談ください。
留意事項
予防接種法に基づく帯状疱疹の予防接種は、自らの意思と責任で接種を希望する場合にのみ接種を受けることができます。予防接種を受ける前に、医師から十分に説明を聞き、必要性や副反応等についてよく理解・納得した上で接種を希望し、予防接種を受けましょう。
ご不明な点がございましたら、予防接種を受ける前に医師や宜野湾市保健相談センターへご相談ください。
なお、明確に対象者本人の接種に関する意思を確認できない場合は、接種することができません。
この記事に関するお問い合わせ先
健康増進課 予防係
〒901-2215
沖縄県宜野湾市真栄原1-13-15
電話番号:098-898-5596
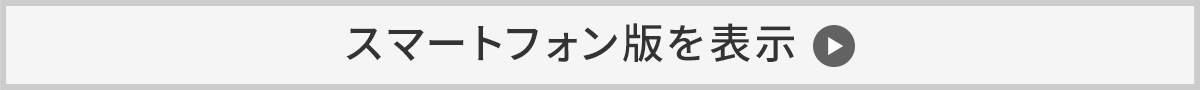






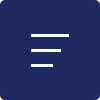
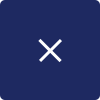

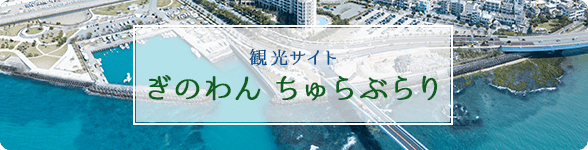


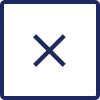









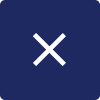

更新日:2025年05月22日