今日の文化課 2024年8月
8月30日 歴史の道を訪ね歩く Vol.6 【宇地泊に潜む戦後沖縄の歴史】
宇地泊から大謝名にかけての古道を訪ね歩いていますが、少し寄り道をして沖縄戦後の宜野湾にも触れてみましょう。
戦後、宜野湾の多くの土地は米軍に接収され、村人も各地の収容所へと移動を余儀なくされました。
帰村が許可されてもなお軍用地として使用され、自分の土地に帰りたくても帰れない住民がたくさんいました。
この宇地泊にも、1970年代まで中規模な米軍基地「キャンプブーン」が広がっていたのです。
58号線の宇地泊交差点から宇地泊に入っていくカーブのかかった割と大きな道がありますね。あの道がキャンプブーンのゲートへと続く道だったようです。
浦添側からその交差点を左に入っていく場合、今でこそ交差点手前に左折専用通行帯があるのでUターンのように入って行かずに済みますが、米軍基地があった時代の写真には専用帯が見えません。

思い切りUターンして入っていたのでしょうか? 答えはNoですね(^^)
ピンと来た方いらっしゃいますか?
そうなんです、当時の沖縄は米軍統治下。車線は右側通行でした。
なので58号線(1号線)から宇地泊に入っていくには、北谷方面からはすんなり右側通行で右折するだけ。浦添方面からも右側車線からの左折なので、わりとゆとりを持って曲がれていたということなんです(^^)
復帰を経て日本となり、1978年7月30日に県内の道路は一斉に車線通行帯を逆転させ、それまでの右側通行から本土と同じ左側通行となって現在に至っています。いわゆる「730」たった一夜での大転換!とんでもない一大事業だったでしょうね(^^;
その730の際、特に問題を抱えていたのが当時県民の足として必須であったバスでした。バスももちろんそれまでは右側通行仕様。運転手は左座席に乗り、各停留所では車体の右側から乗客が乗り降りをしていたわけです。ところが交通帯が逆に変わるとなると、それまでと同じ右側から乗り降りをすると道路のど真ん中!ということになり乗降不可能(^^;
そこで国の補助を得て、その日に向けて約1000台の日本仕様新車バスが導入されました!そんな台数を一体どこで保管していたのか?? それがまさにこちらのキャンプブーン返還跡地だったのです。大半を占める約600台のピカピカのバスが、こちらの跡地で新たな沖縄の道路史をまちかんてぃーしていたんですね(^^)
通行帯が変わったことで、路面店にもいろいろと影響が出たようです。一例では、浦添一の繁華街「屋冨祖」も右側通行の時代は中心地那覇から道なりになんなく入っていくことができたけど、左側通行になってからは道路を挟んで信号待ちをしなくてはならなくなり、素通りされるようになる一因になったとか(^^;?
つい先日建て替えが発表された那覇の歴史ある「みどり駐車場」入口にも、数少ない右側通行の名残が残っていましたが、残念ながら新しく立て替えのためその名残も消失してしまいました。

それでもまだ、日々の生活の中で注意深く目を凝らしてみれば、かつての沖縄が残る痕跡を見つけることができますよ(^^)
普段とは違う視点を意識して「道」を歩いてみましょう♪
ブーン跡地のバス待機は、市立博物館コラムでも紹介されていますよ(^^)
8月28日 歴史の道を訪ね歩く Vol.5 【戦前宜野湾にはトンネルがあった!?】
現代では山道などを貫通する「トンネル」の存在に驚くことはないと思いますが、それが100年も前の沖縄にもあったとなると?驚きですよね~(^^)
しかも、現在はトンネルが一個もない宜野湾にあったとなればさらに驚きません?(野嵩から登又に下りていく立体交差点をトンネルと捉えればトンネルですが^^;)
では、それは一体どこだったか?
なんと現在の大謝名交差点にかつてトンネルがあったのです!

人が歩く道はトンネルの上、その下を「軽便鉄道」が走っていたのです!

え?沖縄に鉄道が走ってた!?と驚く方もいるかと思いますが(^^;
そうなんです、戦前まで沖縄には鉄軌道が走っていたんですよ♪ 本土とくらべてスケールは小さいですが、南は糸満、東は与那原、北は嘉手納まで走っていました。
戦争によって線路もろとも破壊され、それ以降沖縄に鉄道が敷かれることがありませんでした。そのため、戦後のアメリカモータリゼーション文化も相まって、今日の沖縄マイカー所有率の高さにも結び付いているんですね。結果近年の観光客レンタカー利用率にも起因していると思います。
軽便鉄道の内容はまた別の機会にお届けするとして、今回は「宜野湾歴史の道」に絡めたトンネルの紹介を(^^)
実はこのトンネル、先日お伝えした「ジャナマガヤー」から連なる道の真下を通っており、その上を人が歩いていました。となると歩道は割かし高い位置・丘陵上にあったと考えられますよね。
その丘陵にトンネルを通すということは、やはりこのあたりは当時結構な高低差があり、丘陵の形に合わせて道を歩いていたため妙な曲り道「ジャナマガヤー」が出来上がったのではないかなと思ったりします。あくまでも推測ですよ(^^;
ただ、実際現地を訪れると分かりますが、大謝名交差点の一本裏の通りはまさに数メートル土地が低くなっています。この高低差を目にすると、なるほどここを軽便が通り、その上を人々は歩いていたんだな~というのを実感できます(^^)
道も区画もどんどん変化を余儀なくされていきますから、残されているうちにしっかりと目にしていてもらいたいと思います(^^)
8月27日 歴史の道を訪ね歩く Vol.4 【へそ曲がりならぬ謝名曲がり】
最近では「へそ曲がり」という言葉もあまり聞かなくなってきているように感じますが(^^;
へそ曲がりとは、性格が素直ではなくひねくれている人、そのような様のことを表しますね。人の話を聞かずに横を向き、体の中心である「おへそ」が曲がっている様子から生まれた言葉のようです。
今回はそんな「へそ曲がやー」ならぬ「ジャナマガヤー」を紹介しましょう。決して謝名の人がへそ曲がりということではありません(^^;
前回の歴史の道 Vol.3 の続き~
A&W 牧港店前の道から現在の58号に合流し、宇地泊を左手に見ながら100メートルほど北上するとローソンとガソリンスタンドが見えてきます。

このローソンとガソリンスタンドの店舗の間に、58号に対し斜めに進入する細い小道が現れます。
実はこの道も中頭方西海道の道跡の一部で、かつては現58号ではなく、この道が北へ向かう西側のメインストリートでした。
写真でも目にすることができるように、なぜか一旦西側に鋭角に進入し、そして一転逆カーブを描いて東側の大謝名集落へと向かっていました。今でいう「カーブ注意」の標識が出るような!? (逆カーブの跡は既に残っていません)

なぜ曲げていたのか、あるいは曲がらざるを得ない理由があったのか、未だ謎に包まれていますが、その曲がり具合を称して「ジャナマガヤー」と呼ばれていました。
もしかすると高低差(丘陵)の問題があったのかなーなんても思いますが、そのあたりはまた次回(^^)!
以前の市立博物館コラムでも詳細を読むことができますよ♪
8月26日 歴史の道を訪ね歩く Vol.3 【浦添市と宜野湾市の境界にも激オモ歴史スポットが!】
58号線沿いの宜野湾市と浦添市の境界ってどのあたりかご存じですか?
ちょうどA&W 牧港店付近になるのですが、かつて中頭方西海道がこの辺りを通っていて宜野湾間切内ではこちらあたりから始まっていたはずなので、ちょっとだけ浦添側にも寄り道して古道の名残を追いかけたいと思います(^^)

宜野湾間切が誕生するまでは、浦添に隣接する大謝名や嘉数も含め、ほとんどの宜野湾の集落が浦添間切だったこともありますし(^^)
中頭方西海道は首里を起点に浦添グスク、伊祖、牧港へと下ってきて、牧港川を渡り大謝名へ入ってきました。この牧港川を渡る石橋が「牧港橋」で、かつては現在のアウトドアショップ「NEOS」の店舗前の道から橋が架かり、A&Wの前の道へとつながっていました。

実は1853年にペリーが来琉した際、画家ハイネによって当時の石橋が描かれています。その絵には比屋良川や牧港の巨岩(現ポートヒロックが建つ高台)も描かれていますよ♪

過去の文化課コラムで見ることができます。
さらに面白いのは、A&Wの入り口すぐ右横にはなにやら妙な空間があるのですが、駐車場でもないし、公園でもない。しかも接する道路にはなぜか欄干?さらに道向かいは海?


そうなんです。この妙な空間はかつての比屋良川の川筋跡で、川を埋めた名残が今でも空き地のような姿で残っているのです。じゃー比屋良川は現在どこに流れてるの? 皆さんご存じのようにA&W正面左側に流れる直線的な大きな川が現比屋良川ですよね。

古老に聞いた話しの一説によると、実はかつての比屋良川河口は細い上にカーブが多く、大雨になるとすぐ氾濫してしまっていたため、なんとも大胆に川筋を直線仕様に付け替えたとのことです。

↑1970年代の写真 A&W後ろにはっきり川筋が見えます(^^)
機会があればぜひ見学してみてくださいね♪
さーいよいよ中頭方西海道宜野湾編へと入っていきますよ♪
8月21日 歴史の道を訪ね歩く Vol.2【なぜ「歴史の道」を辿るのか】
近世(1671年)に誕生した宜野湾間切には、今でいう国道のような主となる古道が4本通っていました。そのうちの1つに「中頭方西海道」があり、今回返還された西普天間住宅地区跡地にその古の道の痕跡が一部発掘されたわけなのです。
戦後の開発に伴う開発で、昔の人々の生活を偲ばせる道はほとんどその姿を消してしまうか、拡幅されて当時の面影を残す道はどんどん少なくなっています。
なぜ碁盤目状に集落(道)が造られたのか、一里一里に塚が造られたのはなぜだったのか、ワイトゥイとは? 石畳とは? その生活道一つ一つにも、琉球国における政府の政策や人々の生活の知恵、行動などを知ることができるわけです。
「温故知新」という素晴らしい言葉がありますよね。「古きをたずねて、新しきを知る」
人間、歴史から学ぶことがどれほど大切なことか、迷った時には故(原点)に立ち返ることが大きな解決策になる、ということは人類史においても確立されていると思います。
また、琉球・沖縄の歴史文化はやはり日本本土とは異なるわけで、その独特の伝統・文化・生活を知ること、後世にも受け伝えていくことはとても大切なことだと思っています。単に言葉で聞き伝えていくだけでなく、現に残されている往時の史跡を見て、想像し理解していくこと。ここがとても重要だと思うのです。
この道が琉球国時代から使われてた道なの!?という驚きの道が宜野湾にもいくつかあるので、シリーズでお伝えしていきますね♪
お楽しみに~!
8月19日 歴史ロマンあふれる旧道跡を訪ね歩く Vol.1
以前からお伝えしているように、宜野湾市文化課では西普天間住宅地区返還跡地内に残る、琉球国時代からの「道」や「史跡」を発掘し、それらをしっかりと後世にも引き継いでいけるよう国指定文化財「宜野湾歴史の道」を目指し日々奮闘しています。
未だ開発途中のジャングルのような跡地に入って調査をしたり(^^;
古老からの聞き取りをもとに試掘をしたりして、じょじょにその当時の姿を明らかにしてきています♪
ここがいずれは立派な公園となり、その中に古の琉球を感じることのできる「歴史の道」が通ることになるんだな~と想うと感慨深いものがあります。
しかし国内文化財における最も重要性の高い「国指定文化財」を目指すからには、はっきりと指定されるだけの理由がなければなりませんし、史跡が実際にそこに残っていることはもちろん、歴史の道が当時どのような状況で何のためにどう使われていたかという歴史背景もしっかりと伝わるようなストーリーも必要なわけです。
そこで我々は、西普天間住宅地区跡地内に残る歴史の道の指定文化財を目指すのはもちろんなのですが、その道が一体どこから始まっていてどこに向かっていったのかまでを知る必要がある!ということで、現在ではまったく姿を変えてしまった旧道の道跡を追う調査も行っています(^^)
戦前の航空写真やそれこそ琉球国時代に描かれた絵図をもとに、この目の前の道が地図のこの道じゃない!?とか、ここの曲がりがここに残っているコレなはずだ!?などなど。
当時の人々がどのように歩いていたのかを想像しながら歩き調査を行っています。
そのあたりの様子も紹介していきましょうね(^^)
8月16日 ご先祖様、いらっしゃーい!
ご先祖様、いらっしゃーい!
どうも、かつら三線です!(どのくらいの人が苦笑してくれてるでしょうか)
今日(旧暦7月13日)はあの世からご先祖様たちがこの世に帰ってくるお盆の初日「ウンケー」ですね!
そろそろあの世でもこの世でもチムワサワサーしている人で溢れていることでしょうね!
私も業務終わり次第実家に帰りまして、しっかりご先祖のお迎えを行いたいと思います。
というところで、今回はご先祖さま関連で市我如古に所在する「本部御殿墓」を紹介♪
御殿と付く時点で琉球国時代のお偉い方のお墓なんだろうな~と気付く方はなかなか歴史ツウ(^^)
さらに、「御殿で本部!?となると、もしかしてあの空手の大家「本部ザールー」と何か関連が!?」と思ったか方はかなり琉球史レベル高いですね~!
そうなんです、大正期に大阪でロシア人ボクサーとストリートファイトを行い、その巨漢ボクサーを一撃でノックアウトさせたという逸話を持つ本部朝基氏、同じく空手の名手である朝基の兄・朝勇氏の家筋の御殿墓なのです。
彼らの元祖は第二尚氏王統第10代国王「尚質王」6男「尚弘信・本部王子朝平」であり、まさに王族の血を引く空手の大家兄弟なんですね♪
琉球国時代から「空手」は士族の嗜みごとであったので、とくに首里手にいたっては大家に士族出身が多いのは納得ですよね。
そんな世界の空手家から大尊敬される本部御殿の墓が、なぜ宜野湾市我如古にあるのかはまだはっきりとは分かっていませんが、元祖本部王子朝平のすぐ下の弟が「宜野湾王子朝義」であること、さらに二人の母親が同じ(当時国王には妃のほかに複数名妻や側室がいるのは当然だった)だったということ、その母親が中城・章氏の流れで宜野湾に何かしら関わりがあった家系だったからかもしれないとも考えられます。
本部御殿墓の特徴は、前庭が二段構えになっていて石積みで分けられていることから、従者用と王族用で使い分けられていたと推察されること。また墓に続く約60mにもおよぶ里道が二か所直角に折れ曲がっており、ヤナムンゲーシの意味があると考えられるとのことです。
われわれも、御先祖様あってこそ自身の今日がありますよね。
しっかり日々の感謝を伝え、お盆をうとぅいむちで迎えましょう(^^)
【本部御殿墓 市指定文化財 史跡】
8月13日 旧盆だからこそ!? 宜野湾の古老の昔話を聞こう♪
いよいよ沖縄では今週末から旧盆を迎えますね(^^)
沖縄ではまだまだ旧の暦で動くことも多く、特にお盆は旧暦に合わせて行事を行うため旧暦の7月13、14、15日(今年は新暦の8月16、17、18日)は帰省客でも賑わいます。
県外に住む家族へ、ほかの行事はいいからお盆だけは帰ってきなさい!という声も未だ根強く残っており、その期間は飛行機がとても取りにくいという沖縄ならではの会話は毎年恒例です(^^;
いかに先祖を大事にしているかを分かってもらえる、古来からの風習の一つかと思います。
今では全国区となった「エイサー」も、盆にあの世から戻ってきた御先祖さまたちを、再びあの世へ御見送りする際に踊られてきた念仏踊りが起源となっていると言われているんですよ(^^)
そんな旧盆中日の17日土曜日になりますが、「第二回野嵩スディバナビラ石畳道文化講座」が野嵩一区公民館で行われます。

今回は「昔の野嵩とスディバナビラの思い出」と題して、戦前生まれの野嵩出身の古老お二方に昔の思い出話を語っていただきます(^^)
戦前生まれの方のお話を聞ける機会は、本当にどんどんと少なくなってきています。
ぜひこの機会に古の野嵩、ウチナーの昔話に耳を傾けてみませんか?
講座は17日午前10時~午後12時 午前9時半より受付開始です。
多くの方のご参加お待ちしております!
*駐車場がございませんので、お車でお越しの際は宜野湾市役所に車を駐車していただき徒歩で来られるようお願いします。徒歩10分くらいです。なお、足に負担がある方、事情のある方は相談可能ですので、前日までにご連絡ください。
8月6日 森の川の拝所をでっかいアイツが占拠していた!救護!
文化課では、定期的に文化財の様子に変わりはないかのパトロールおよび清掃作業を行っています。文化財は私たち市民の大切な財産ですので、後世にも変わりなく残していくべく保護活動の一環として行っています。
時に草刈り、木々の剪定、土砂浚い、ごみ拾い、案内板・注意板設置などなど様々な作業を行います。
そうこうしているなか、時には思いがけないいろんなハプニングにも遭遇します(^^;
先日のハプニングもなかなかの出来事でした(^^;
真志喜に県指定名勝「宜野湾市森の川」がありますね。察度王ゆかりの羽衣伝説の舞台にもなっている湧泉です。1725年に向氏・伊江家の人々によって石造で整備されたと伝わります。
水が湧き出ている樋の後ろ側には、香炉が祀られている石積みで囲われた拝所スペースがあります。そちらももちろん毎回チェックするのですが、今回なんと!結構な大きさの木が倒れ落ちていて完全に拝所スペースを塞いでしまっていました。
この間襲来した台風の影響だと思われます。
拝みに来られる方も多い拝所なので、その場ですぐに撤去作業開始!さすがに入り口からは取出せないし、上から引っ張り上げるにもこれはあまりに重過ぎる(^^;
車からノコギリを持ち出して、3分割にして処理しました!
ただ、、拝んでいる人がいる時に倒れ落ちていたらと思うとゾッともしますね。。今後は倒れ落ちそうな木がないか頭上も気にしながらパトロールをしていきたいと思います。
皆さんも機会があれば泉奥のこちらの拝所までご覧になってみてくださいね。実はここから水が湧き出て地下の暗渠を通り表の樋に流れ出ているんですよ♪
とても神聖な場所になっていますので、見学される方は「リスペクト(尊重)」の気持ちをどうぞ忘れずにお願いいたします。
8月4日 令和6年度「イガルー・シマ文化財教室」始まりました(^^)!
令和6年度イガルー・シマ文化財教室『屋取集落を知る』
第一回目『宜野湾の屋取について』
大盛況のうちに終えることができました😁
駐車場も即満杯で、あと数台来られるとどうしようかと心配になるくらいでした😅
ご参加くださった皆さん、ありがとうございました〜!
やはり歴史好きにとっても「屋取」という概念は、なかなか未だコレといった確証たるイメージを持ちにくい部分もあるためか、皆さんかなり真剣に興味深く聴講されていました♪

那覇市歴史博物館・鈴木悠先生のお話は、琉球士族という概念から年代ごとの士族人口の移り変わり、そして士族と屋取との関わりという、段階的で具体的な説明がとても分かりやすかったです♪
講和後の質疑応答も時間が足りず😅
アンケートにも質問事項を書いてもらったのですが、質問数の多さや内容も鋭く、皆さん本当に興味深く聞かれていたんだな〜と運営サイドも嬉しくなりました♪
次回(9月7日 10:00~12:00)は同じく長田公民館にて、『長田の地形と歴史』というテーマで沖縄国際大学の崎浜靖先生に講和をお願いしています♪
なぜ宜野湾の東部に屋取集落が多いのか、それらは土地的にどのような特徴があるのかなどを学べますよ😁
実は申し込みはすでに受付終了してはいますが、、
どうしても聞きたい!という方は、まずは文化課までご連絡ください😁
宜野湾映え!大謝名メーヌカーとシークヮーサー!
So ウチナー!大謝名メーヌカーとシークヮーサー(^^)!
なかなか映える!?ウチナーコンビネーションかな~と思って撮ってみました♪

*大謝名メーヌカー:市指定史跡
シークヮーサー(和名:ヒラミレモン)は別称「クニブ」とも呼ばれたりしますが、「クニブ」は「九年母」と書き、植えてから実が成るまでに九年かかることからそう呼ばれるようで、実は沖縄で育つ在来種の柑橘類は相称して「クニブ」とも呼ばれてきました。
そこで語呂合わせとして沖縄では、9(ク)月22(ニブ)日を「シークヮーサーの日」として制定しています(^^)
シークヮーサーが有名な場所として大宜味村があがりますが、大宜見も宜野湾も近世17世紀になって新設された新しい間切(現在の市町村)なんですよ(^^)
そんな間切時代の宜野湾も学べる「イガルー・シマ文化財教室」が今週からスタートします!
当日受付も可能ですので、申し込みするの忘れてたー!という方もぜひご参加ください(^^) 今月の講座は長田公民館で8月3日土曜日午前10:00からです♪

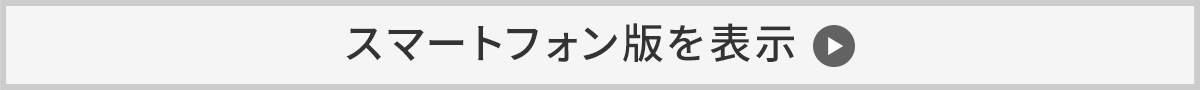






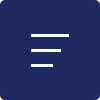
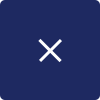

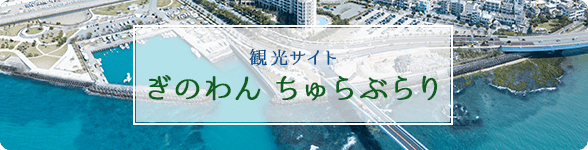


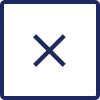









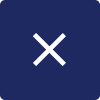








更新日:2024年09月03日