今日の文化課 2024年11月
11月28日【喜友名泉見学者 from 東京】
本日は、東京から観光🛩で沖縄にいらっしゃっている方からのご希望で、喜友名泉の見学に同行してきました😄
*喜友名泉は普段施錠していますので、見学の際には文化課の立ち合いもしくは喜友名自治会への申し込みが必要となっております。
歴史や文化財へのご関心が高いようで、本日は普天満宮にも足を運んでいらっしゃったようです♪
話しが弾みに弾み😅 湧水の話から沖縄の風習の話、歴史や文化の話などなど、本土と沖縄の違いに終始驚いていらっしゃいました😄
特にその石の文化、そして昔からの人々の暮らしの様子にも大変興味を持ってくれて、説明する側も説明のし甲斐が大いにありましたよ♪
ますます沖縄に興味を持ってもらい、帰途についてもどんどんと周りの方々へ沖縄の歴史文化の関心度を高めてもらえると嬉しいですね😄
と、喜友名泉には今やもう住人(住鳥?)となっているバリケン🦆がいるんですが、今日はまさかの樋の奥から顔を覗かせてました😂

初めて訪れる人が見たらシカぶ(ビビる)よやー😂

ハリケーン中だけにしてくれ😂
ちがうかー🤣
#文化課 #湧水 #歴史の道 #国指定 #喜友名 #歴史 #石積み #kiyuna #チュンナーガー #琉球
11月25日 【伊佐の三叉路で交通安全を願う炎】
まだまだ続きますよ~伊佐ネタ!
58号線と普天間から58号線に下りていく県道81号線が重なる伊佐三叉路は、県内でもワースト上位に入るほど事故が多い交差点としても有名ですよね。これは決して誇れるものではないのですが。。
実際に走ってみると分かるかと思いますが、私自身もハッとさせられた経験があります😨
現在では三叉路の北側に新しく十字路の伊佐交差点もでき、以前ほどのような危険性はいくらか緩和されているようですが、昔はもっと危険だったんだろうと想像されます。
そのような県内きっての交通量の多い交差点に、1965年交通安全の願いを込めて建てられた塔があります。
それが「交通安全之塔」です。

今では道路通行帯が逆になり(もしかしたらそれが事故数を増やしている原因なのかもしれないけど)、塔は伊佐三叉路に出来た三角州のような場所に位置しているので気を付けて見ないと気付きにくいかもしれません😅
が、事故も多い場所なのでよそ見運転は止めましょうね😅 塔を見るために事故なんか起こしたら本末転倒ですからね😅

実はこの塔、以前にも紹介した沖縄平和祈念像の作者である宜野湾にも所縁の深い「山田真山」画伯がデザインしたものなんです😄
文字は沖縄の三筆に数えられる能書家の謝花雲石氏♪
1964年の東京オリンピックが行われるにあたって、聖火ランナーがこの三叉路を走り上っていったことを記念して「聖火」を象ったデザインになっており、また運転者や歩行者の交通意識の高まりを願って建てられたといいます。
自動車普及率が高い沖縄県だからこそ、事故が多いのは致し方ないのかもしれないですが、一人一人が意識を高めれば少なくすることはできると思います😄
山田真山画伯の想いにも応えられるように、安全運転を心がけましょうね♪
11月22日 【ハイレベルな琉球国の測量技術と現存する基準点】
引き続き伊佐ネタでいってみましょう♪
みなさん、印部土手石(ハル石、印部石とも)という琉球国の歴史に関わる重要な石を見たこと聞いたことありますか?
この石は、琉球国時代の乾隆検地(1737年~1750年)という土地調査の際に、田畑などの土地を一筆ごとに測量するため設置された図根点(基準点)なのです。
石には、ひらがな、カタカナ、変体かなのいずれか一文字が順序を示す記号として彫られていますが、何を基準にどの順番で定められていたのかはっきりとは分かっていません。さらに記号とともに所在原名(小字名)も彫られており、その土地が昔なんと呼ばれていたのかを知る事ができる貴重な資料にもなっています。
各間切(現在の市町村に相当)ごとに200~300個の石が設置されたといわれていて、その重要性から地方役人には年に二度の点検が義務付けられていたといいます。
印部石を基準にした測量は、当時の世界最先端の技術でした。フランス式の測量術で清国を通して導入されたと考えられています。その精度は現在の地図と比較しても遜色なく、日本本土よりも早い段階でこれほどの精度の高い測量技術を持っていたんですよ😄
しかし廃藩置県を経て、1899年~1903年の土地整理事業の際に印部石のほとんどが消失してしまい、現在では100基ほどが確認されていますが、土手石として現地にそのまま残っているものはほんの僅かしかありません。
その僅かの中のいくつかが、ここ宜野湾の市内にも現存しているんです!(基地内にもある)
その一つが喜友名区にある「ワ たけたう原」の印部石!
あれ?伊佐の話だったんじゃないばー?
ま、いーさ😂!?
えーひゃ、いさんちゅーにヌーらりんどー😂
ドテー!
いえ、そうなんです、実はここにも珍しさダブルポイントの面白さが😄
実際にこの「ワ たけたう原」が現存している地番は喜友名区内、なんですが、
1963年の新行政区設置の際に、伊佐の小字「上原」の一部が喜友名区に編入されたため、元来は伊佐村の小字上原に建てられたはずの印部石にも関わらず、現在は喜友名所在となっているのです😁
ただ、石に書かれた「たけたう原」という地名はすでに消失し、いくつかの小字が合併して「上原」になったのではと考えられていて、このように既に消えてしまった土地名の名残を残すうえでも印部石は貴重な歴史遺産といえるのです。
ちなみに、ただいま開発真っ最中の西普天間住宅地区内返還跡地でも印部土手石が昔変わらずの状態で発見されました!
が、開発に伴い撤去を余儀なくされ、今は市立博物館の駐車場内に移設して展示保存されていますよ♪
さらに、博物館内でも3つの印部石を見ることができますし、いろいろな歴史文化の勉強にもなるので、ぜひ訪れてみてくださいね😄
伊佐「たけたう原」の印部土手石にも、実際に足を運んで古を感じてもらえると嬉しいです♪
【伊佐「たけたう原」銘の印部土手:市指定史跡】
場所:https://maps.app.goo.gl/bB8tVge1uJ1LKhao8
11月20日 【野嵩にてリアルエビカニックス!?】
昨日、今日はマンスリーで行っている文化財パトロールに行ってきました♪
市内に所在する登録文化財に変わった様子はないか、見学する際に不都合となるようなことはないか、草刈りをしたりゴミ拾いをしたりなどを含めて定期パトロールを行っているんです😄
そこで今回は、パトロール中に結構レアな一場面を見ることができたので紹介しましょう♪
野嵩に「野嵩クシヌカー」という湧水があります。
こちら市の指定史跡に登録されています。
2021年に大規模な改修工事が行われて、とても見学しやすくなっているんですね😄

今でも水がコンコンと湧き出ていて、貯水槽内にはメダカも多く泳いでいるので子供たちの格好の遊び場にもなっているんです😁
なので、、仕方ないといえば仕方ないのかもしれないんですが、パトロール時にはほぼ毎回といっていいほどお菓子の袋のポイ捨てや空き缶、ジュースパックなどなどのゴミが置き去りにされていたりします。(タバコのポイ捨てやアルコール類のポイ捨ては仕方ないでは済まされないですよ!)
大切な自分たちの財産である文化財、もっと大事にしてもらえるよう意識してほしいなと思います。みなさんもお子さんたちへのお声掛け、できる限りお願いできればと思います。
と、今日もゴミは落ちてるのかなーと思いながら階段を下りていくと、
お!なんと素晴らしい!ゴミがほぼない!嬉しーさー😁
と感心していたら、
なんとなんと貯水槽の中ではエビ同士が向かい合って🦐、今にも鋏でチャンバラを行いそうな態勢!

しかも結構な大きさ!

より近づいてみると、二尾とも高速バックジャンプで身を隠してしまいました😅
そしてそして、逆の方に目をやると、そこにはまさかのカニ!!

これってまさかの!リアルエビカニックスやさにー😁
おもわずその場で踊ってしまいました、というのはユクシーです😅
いや、もしかしたらこちらのエビカニたちは、これだけ綺麗な状態のカーだからこそ嬉しくなって悠々と表に出てきたのかもな~って♪
生き物にも優しい宜野湾シティー、宜野湾ピーポー目指していきましょうね♪
(野嵩クシヌカーについての文化財情報はまた別途取り上げますね😄)
11月19日 【58号線の下に埋もれた伊佐の二つのカー】
伊佐にはフンシンガーのほかにも、ウブガー(産泉)、ウフガー(大泉)という水量豊富な湧水がありました。
が、戦後米軍の道路建設にともない、58号線の真下に埋められてしまいました。
当時の沖縄水事情はとてもとても安定的なものではなく、湧水はものすごく大事な水源。
ということで、埋めた側から自然に湧き出てきた水を溜められるように改修して、58号線より西側に新たに二つの水源地を確保したのです。
現在でもかなりの水量を誇る二つのカーは、
伊佐川バス停の道路下に一つ

そして伊佐浜交差点を西向けに曲がったところすぐにもう一つがあります。ここには取水ホースも整備されていて、たまに取水している車も見かけますよ♪

なかなか車で通っているだけでは気付かない、カーだとも分からないかもしれませんが😅
見ているだけで癒される水の流れ♪ そして地域の拝みの対象でもあるカー♪
ぜひ訪れてみてもらえればと思います😄
11月18日 【伊佐に鎮座する名物シーサー】
伊佐浜の話をいくつか紹介したところで、続きましては伊佐ネタをピックアップしていきましょう😁
伊佐もほんと水どころで、今でもコンコンと湧き出る湧水がいくつもあります。
その一つが「フンシンガー」
昔からこの地域の人々の生活用水として使われ、その水量もさることながら大雨の日にも濁らない貴重な水源だったようです。
他のカーと違って珍しいのが、香炉が置かれている台座の前に鳥居まであって、より荘厳さを放っています😄
1953年に今の形に改修されていますが、1970年代の写真では泉内をプールのように遊ぶ子供たちの姿が写っていて、それは楽しい遊び場にもなっていたようです😁
当時の写真はこちらから見れますよ♪
そしてこのフンシンガーの湧き水を利用して整備されたのが「ふんしんせせらぎ通り」
住宅街の中に通る小道なんですが、道沿いに水路が流れていて歩くととっても気持ちがいい通りなんです♪
1982年には国土交通大臣から「手づくり郷土賞」を受賞しているんですよ😄
さらに驚きなのが、なんとこの小道入り口には石造りのシーサーが鎮座していて、そのシーサーの口からは水がドバドバーと出ているんです!
宜野湾のマーライオンと呼ばれてるとか呼ばれてないとか😁

ぜひ会いに行ってみてくださいね♪
11月13日 【謎のベールに包まれる喜友名グスク】
これまでにも何度かその存在は紹介している「喜友名グスク」
地元では喜友名のことをチュンナーと呼んでいますが、喜友名グスクも「チュンナーグスク」と呼ばれていたようです。ちなみに喜友名泉も「チュンナーガー」ですよ😄
そう、喜友名にはかつてグスクがあったんですね。
え”!?という感じですよね😅
現在の県道81号沿いの、米軍普天間ハウジング跡との間にあるフェンスあたりです。
群道整備や戦後のハウジング建設のために跡形もなく破壊されてしまいました。
ただ戦前のグスクの姿を覚えている古老がわりといらっしゃって、そこに存在していたことは間違いようです。
堅固な野面積みの石垣で画され、正門と裏門があり、擁壁は高さ3mほどもあったといいます。
しかしグスクについてのより詳しい情報は残っておらず、誰が築城したのか、だれが居城していたのかなどについては未だ謎に包まれているのです。
伝承として、北谷グスクとの争いがあったと伝わりますが、実際にその地に立つと北谷グスクの姿がはっきりと捉えられ、確かにお互いを意識し合っていたんだろうな~と想いを馳せることができます。

↑写真中央の丘陵台地が北谷グスクです。

↑実はこの58沿いの丘陵なんです。普段何気なく通ってません😅?
さらに、いつの時代のものかははっきりとしませんが、喜友名グスク跡現地ではわずかに石積みの遺構を見ることができたり、明らかにグスクへ繋がっていたであろうかつての「道」を感じたりすることができます。

将来はこの部分も公園エリアとして整備される方向なので、開園した際には沖縄を代表する絶景ポイントになるんじゃないかなと本気で期待しています♪

癒しの湧水群あり、歴史の道あり、グスク跡もあり、琉大病院まである!
今後宜野湾を代表するエリアになっていきそうですね😄!
11月12日 【返還された喜友名の拝所「フトゥキアブ」】
本日は、今週末に行われる「喜友名グスク見学会」の現地最終安全確認に行ってきました😄
あれ?😅 このジャングルエリアの草刈ったのって、、10月半ばでまだ一か月も経ってないと思うんですけどー、、すでに草が伸び始めているー😂
改めて自然の生命力のすごさを実感するのと、これぞまさしく雑草魂なのか!と感動すら覚えます😅 毎度思うんですが、、これらの刈ってしまった大量の草を、どうにか有効活用できるといいんですけどね~。。
この地にヤギでも放牧できたら、ヤギのパラダイスだとも思うんだけどなー😂
さて、今回の見学会メインテーマの一つが喜友名の「フトゥキアブ」
このほど返還された米軍西普天間住宅地区内に所在しており、今後公園緑地整備に伴い皆さんの目に触れられる日も近いことでしょう♪
喜友名集落の昔からの拝所で、人々の大事な拠り所ともなっている聖なる洞窟でした。

かつて洞内には風化著しい人骨が散乱していたことから、墓として利用されていた時代があったことも考えられるようです。

見学できるのは洞入り口から数メートルの範囲ですが、実は全長約50mの長さがあり、最大洞幅は16m、天井は高いところで約5mもあります。
鍾乳石が織りなすアートも絶景ですよ♪
戦前までは喜友名グスクに次ぐ喜友名の拝所で、年中の折り目に拝んだとされています。旧暦の9月9日にはフトゥキアブを拝んでから普天間権現に詣でたといいます。

戦時中は喜友名集落の避難壕の一つとしても利用されました。
見学会を通して、今後どのような整備保存が有効で望ましいかなどの市民の声も聞きながら進めていく方向です😄
今後も順次見学会を開催していければと思っていますので、皆さんの関心度合もどんどん高めてくださいね~😄
11月9日 【宜野湾歴史の道文化財教室 第二回講座も大盛況!】
本日、宜野湾歴史の道文化財教室第2回目講座が無事終了しました〜!
朝からのあの豪雨で、、受講生ちゃんと来てくれるかな😨 と心配しましたが、
もしかしたら本年度で最多の受講生数だったかもです😁
室内が熱気に溢れていましたからね😁

第2回目の講座は、宜野湾市にある4本の歴史の道についての紹介。
そしてその道たちがどういう変遷を経てきたのか、どのような特徴があるのか、道沿いにはどのような文化財があり、生活の跡が見えるのかなどなどを思い切り詰め込んで紹介してくれました😁
まだ全てを読めてはいませんが、アンケート用紙への質問や感想もかなり書き込んでもらっていたようで、どんな内容なのか今から楽しみです♪
第3回目は来月12月の21日土曜日、同じく市民図書館2階にて13時からとなっています♪
次回はさらーに!深掘りして、まさに掘って出てきた発掘調査の内容などをお届けします😁
皆さんのご来場お待ちしておりまーす!
本日はたくさんのご参加ありがとうございました♪
11月8日 【伊佐浜に残るかつての護岸と海を物語る佐阿天橋碑】
先日の「伊佐浜水源地 豊之泉」に続いて、
「伊佐浜」に関する文化財ネタをもう一つ😄
こちらの文化財は民間地に所在しているので、誰でもすぐにでも見に行けますよ♪
それが【伊佐浜「新造佐阿天橋(さあてんはし)碑」】という石碑です。
地番は伊佐、宜野湾バイパスと国道58号の交わるあたりで、特別養護老人ホーム愛誠園さんのすぐ目の前になります。
以前は伊佐市営住宅が建ち、目の前には公園もあって木で隠れて気付きにくかったんですが、今では道路からでもはっきり見えますよ😁
場所はこちら
実は現在建っている碑はレプリカなんですが、オリジナルは宜野湾市立博物館に収蔵されています。
石碑表裏の碑文が長きにわたる摩滅によって判読できない状態になっており、2000年に復元整備が行われました。
碑文の内容は、佐阿天川(現在の普天間川)に佐阿天橋を架けた経緯を記しており、
簡単に要約すると
「東側(内陸側)には首里・那覇に行く正路があるが、道が険しくて容易ではない。皆その道は通らず平坦なこの道を通る。しかし普段川を渡れても大雨の時には氾濫して渡れないので1820年にこの橋を建設した」
という内容です。
実際には普天間川と碑とは500mほど離れているのですが、なぜここに?
碑の前に広がる綺麗な砂浜などの景色に合うよう、このあたりに建てたのでしょうか😁
え??ぬーいっとんば?海はもっともっと奥でしょ?
と思ってしまいますよね😁
実はこの石碑の目の前はかつて、真っ白で綺麗な砂浜が広がる風光明媚な場所だったのです♪
碑は沖縄戦で根元から折れてしまい行方不明になっていましたが、戦後伊佐浜の海で発見され建て直されました。

↑海岸を埋め立てる前に撮られた写真 (写真集「ぎのわん」)
そして同じ角度で撮ってみた現在の写真がこちら↓
碑の前の護岸はその当時のまんまなんです!
どれだけの規模が埋め立てられたかよく分かりますよね♪
そしてこの石碑のすぐ側を軽便鉄道が走り、波が高い日などは乗客は波をかぶっていたともいいます😄
護岸からそのまま北前向けに行くと普天間川に突き当り、その川には「軽便橋」という人が一人通れる細さの橋が新しく架けられています。
はい、軽便がかつてそこを通っていたという名残なんですね♪
というような伊佐浜の佐阿天橋碑にも記されている琉球王府時代の「歴史の道」!
の第二回目講座が明日9日土曜日の13時から宜野湾市民図書館で開催されますよ~♪
当日受付も可能なので、興味がある方は足を運んでくださいね😄
伊佐浜「新造佐阿天橋碑」:市指定史跡
11月7日 【返還地に残る戦前の遺構と幻の地名刻字泉】
西普天間住宅地区返還地には、その特殊な経歴のためか戦後から手つかずのまま放置されてきた重要な史跡・遺構が数多く残っています。(基地建設造成時に埋められてしまったものも含めると相当数になると思われます)
その一つに「豊之泉」と刻まれたコンクリート製の祠のような遺構があります。

庇のような部分には信仰の対象を表す香炉も祀られています。
着工1959年2月、竣工1959年3月とも刻まれ、
さらに興味深いのが「伊佐浜水源地」と刻まれていることです。

伊佐浜といえば、みなさん「伊佐浜の土地闘争」でその名を聞いたことがあるかもしれません。
戦後やっと地元である伊佐浜に戻ってこれた住人や、米どころであった伊佐浜のターブックヮー(水田)がようやく息を吹き返してきたころに、基地拡張のため問答無用で再び土地を奪われ強制立ち退きをさせられた一大事件です。「銃剣とブルドーザー」としても知られますね。
その際、戦後伊佐浜の人が自分たちで汗水流して造り上げた簡易水道も壊され、その代償として米軍が基地内に建設した貯水施設からパイプを敷き水を引くことを許可されました。
その後地元住民が米軍の許可を得て基地内で水源地整備作業を行い、完成記念としてこれらの文字が刻印されたというわけです。
”この湧水の豊かさを誇り、我々にいつまでもこの水の恩恵を与えてくださるようにとの願いを込めて「豊之泉」と刻字した。”とのことです。(伊佐誌より)
そのような歴史を知り改めてこの遺物を見ていると、その当時の地元の方々の大変なご苦労が目に浮かんできます。
現地では今でも米軍の貯水施設、そしてそこから伸びるパイプも見ることができます。水もまさに、とても豊富な量で湧き続けていますよ♪

将来、この地区が公園整備の対象となっていく際には、おそらく老朽化したこれらの設備などは撤去されていくのかと思いますが、今では行政地名としては消失してしまった「伊佐浜」の刻字が残る貴重な遺構は、今後も大事に整備保存していければと思っています。
また、将来この伊佐浜エリアを見学できるようになった際には、史跡から読み解ける沖縄ならではの重大な歴史も共にしっかりと学んでいければと思います。
11月5日 【イガルー・シマ講座第四回目は「真栄原~佐真下まち歩き」】
去った土曜日はイガルー・シマ文化財教室第四回目「真栄原~佐真下のまち歩き編」を行いました😄
先月行われた第三回目の「真栄原~佐真下よもやま話編」の座学を経て、実際に昔使われていた古道や史跡、道中に纏わる昔話などを交えて約2時間のまち歩きを行ってきましたよ♪

嘉数~真栄原~佐真下を通っていた普天満参詣道の名残、嘉数国民学校跡、ヒャーガーラ橋、真栄原のウブガー、ヒャーガーラカジマヤー(旧真栄原十字路)、ナガサクガマ、キングスクール、真栄原のウブガーなどなどを解説を交えて歩きました。
今回も地元の方々の参加が多かったようですが、「地元なのにこんなとこがあったなんて知らなかった!」「毎日通ってる道が、昔は国王が通った道だったのか!」などなど皆さん驚きが絶えなかったようです😄

普段何気なく通ってる道や風景にも、遡ってみると非常に興味深い歴史が隠れていたりするんですよね♪
それらを知ってから見える景色は、それまでのものとは全く別物にも見えたりするから面白い😄

今回で全8回講座の半分が終了し、来月からは後半の部が始まり「中原」~「愛知」へと移っていきますよ~♪
後半の部からのご参加もお待ちしております😄
と、その前に今度の土曜(9日)には「宜野湾歴史の道文化財教室」の第二回目講座が市民図書館で行われます。
今回は、琉球王府時代から宜野湾で利用されてきた「歴史の道」の概要と、西普天間住宅地区返還地内で発掘された貴重な文化財の数々をお伝えしますよ♪
今後の宜野湾の見え方すら変わってくるかもしれない楽しい講座内容となっていますので、多くの方のご参加お待ちしておりまーす(今から受付もOK)!
お申し込みはこちらから

11月1日 【返還地草刈り作業も後半戦!喜友名から新城への道】
本日も絶賛草刈り作業行ってまいりましたー🫡

今日も西普天間返還地内の、旧新城集落あたりをバリバリ刈ってまいりました😁

だいたいこのあたり
こちらにもいまだにコンコンと湧き続ける泉がいくつもあり、その豊富な水を米軍が利用したコンクリートの貯水槽が残っていたり、長年かけて水の流れが作った澤があったりと大変興味深いエリアです♪


こちらも今後公園として整備し残していく予定ですので、史跡たちも皆さんの目に触れられる日を楽しみにしていると思いますよ😁
さー明日から三連休ですね!
文化の日ウィークエンド、文化や文化財と触れ合う時間を持ってみてはいかがでしょうか♪
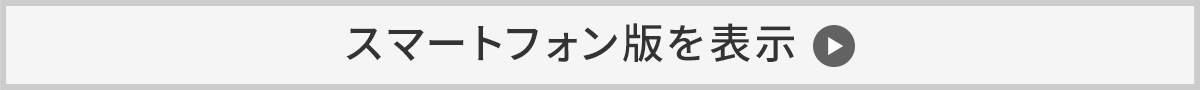






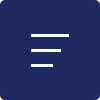
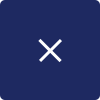

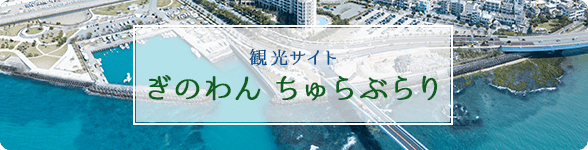


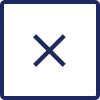









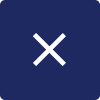









更新日:2024年12月02日