老齢基礎年金
老齢基礎年金は、国民年金加入者であった方の老後の保障として給付されます。
20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金の加入期間等に応じて年金額が計算され、原則、65歳から老齢基礎年金を受けとることができます。
老齢基礎年金の受給要件
老齢基礎年金を受け取るためには、保険料納付済期間と免除期間などを併せた10年以上の資格期間が必要です。
| 納付期間 +免除期間 + 厚生・共済年金納付期間 + カラ期間 ≧ 10年 |
※カラ期間(1~3)は、資格期間に含まれますが、年金受給額の計算には含まれません。
- 昭和61年3月以前の厚生年金等の加入者の被扶養配偶者であった期間
- 平成3年3月以前の学生であった期間
- 20歳から60歳になるまでの間で、海外に住んでいた期間 …など
※学生納付特例期間は資格期間に含まれますが、年金受給額の計算には含まれません。
年金額
令和7年度の年金額(満額)
年額831,700円(月額69,308円)
※昭和31年4月1日以前に生まれの方は、年額829,300円
※20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
受給開始時期
原則として65歳から受給できます。65歳後に受給資格期間の10年を満たした方は、受給資格期間を満たしたときから老齢基礎年金を受け取ることができます。
60歳から65歳までの間に繰り上げて減額された年金を受け取る「繰り上げ受給」や、66歳から75歳までの間に繰り下げて増額された年金を受け取る「繰り下げ受給」を選択することができます。
繰上げ受給 と 繰下げ受給
【繰上げ受給】
年金は原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば、本来の受給開始年齢よりも早い時期に受け取ることができます。
繰上げ受給は、60歳から65歳になるまでの間に請求することができます。
ただし、繰上げ受給を請求した時点に応じて、65歳までの月数ごとに一定の率で減額されます。減額された年金は、繰上げ請求した月の翌月分から受け取ることができます。
※繰上げ請求をする際は、以下の点にご注意ください。
- 老齢年金を繰上げ請求すると、繰上げする期間に応じて年金額が減額されます。生涯にわたり減額された年金を受給することになります。
- 繰上げ請求すると、請求した日の翌月分から、年金が支給されます。
- 老齢年金を繰上げ請求した後は、繰上げ請求を取消しすることはできません。
- 老齢年金を繰上げ請求すると、国民年金の任意加入や、保険料の追納はできなくなります。
- 共済組合加入期間がある場合、共済組合から支給される老齢年金についても、原則同時に繰上げ請求することとなります。
- 繰上げ請求すると、厚生年金基金から支給される年金も減額される場合があります。
- 65歳になるまでの間、雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付が支給される場合は、老齢厚生年金の一部または全部の年金額が支給停止となります。(老齢基礎年金は支給停止されません。)
- 厚生年金保険に加入した場合のほか、国会議員や地方議員になった場合には、給与や賞与の額に応じて、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。(繰上げ請求した老齢基礎年金は支給停止されません。)
- 繰上げ請求した老齢年金は、65歳になるまでの間、遺族厚生年金や遺族共済年金などの他の年金と併せて受給できず、いずれかの年金を選択することになります。
- 繰上げ請求した日以後は、国民年金の寡婦年金は支給されません。寡婦年金を受給中の方は、寡婦年金の権利がなくなります。
- 繰上げ請求した日以後は、事後重症などによる障害基礎(厚生)年金を請求することができません。(治療中の病気や持病がある方は注意してください。)
- 老齢厚生年金の繰上げ請求をした場合、厚生年金保険の長期加入者や障害者の特例措置を受けることができなくなります。
- 老齢厚生年金や退職共済年金を受給中の方が繰上げ請求すると、これらの年金に定額部分の支給がある場合は、定額部分は支給停止されます。
〈繰上げ受給の減額率について〉
65歳から受け取る年金額を100%とした場合
【昭和37年4月1日以前生まれの方】 繰上げの月単位で受給率が異なります。
| 年齢 | 0カ月 | 1カ月 | 2カ月 | 3カ月 | 4カ月 | 5カ月 | 6カ月 | 7カ月 | 8カ月 | 9カ月 | 10カ月 | 11カ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60歳 | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 | 75 | 75.5 |
| 61歳 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 |
| 62歳 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 |
| 63歳 | 88 | 88.5 | 89 | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 | 93.5 |
| 64歳 | 94 | 94.5 | 95 | 95.5 | 96 | 96.5 | 97 | 97.5 | 98 | 98.5 | 99 | 99.5 |
【繰下げ受給】
年金は原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば、本来の受給開始年齢よりも遅い時期に受け取ることができます。
繰下げ受給は、66歳から75歳になるまでの間に請求することができます。繰下げ受給を請求した時点に応じて、65歳までの月数ごとに一定の率で増額されます。増額された年金は、繰下げ請求した月の翌月分から受け取ることができます。
※繰下げ受給を請求する際の注意事項
・加給年金額や振替加算額は増額の対象になりません。また、繰下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)中は、加給年金額や振替加算を受け取ることができません。
・75歳に達した月を過ぎて請求を行っても増額率は増えません。
・年金生活者支援給付金、医療保険等の自己負担や保険料、税金に影響する場合があります。
〈繰下げ受給の受給率について〉
65歳から受け取る年金額を100%とした場合
| 年齢 | 0カ月 | 1カ月 | 2カ月 | 3カ月 | 4カ月 | 5カ月 | 6カ月 | 7カ月 | 8カ月 | 9カ月 | 10カ月 | 11カ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66歳 | 108.4 | 109.1 | 109.8 | 110.5 | 111.2 | 111.9 | 112.6 | 113.3 | 114 | 114.7 | 115.4 | 116.1 |
| 67歳 | 116.8 | 117.5 | 118.2 | 118.9 | 119.6 | 120.3 | 121 | 121.7 | 122.4 | 123.1 | 123.8 | 124.5 |
| 68歳 | 125.2 | 125.9 | 126.6 | 127.3 | 128 | 128.7 | 129.4 | 130.1 | 130.8 | 131.5 | 132.2 | 132.9 |
| 69歳 | 133.6 | 134.3 | 135 | 135.7 | 136.4 | 137.1 | 137.8 | 138.5 | 139.2 | 139.9 | 140.6 | 141.3 |
| 70歳 |
142 |
142.7 | 143.4 | 144.1 | 144.8 | 145.5 | 146.2 | 146.9 | 147.6 | 148.3 | 149 | 149.7 |
| 71歳 | 150.4 | 151.1 | 151.8 | 152.5 | 153.2 | 153.9 | 154.6 | 155.3 | 156 | 156.7 | 157.4 | 158.1 |
| 72歳 | 158.8 | 159.5 | 160.2 | 160.9 | 161.6 | 162.3 | 163 | 163.7 | 164.4 | 165.1 | 165.8 | 166.5 |
| 73歳 | 167.2 | 167.9 | 168.6 | 169.3 | 170 | 170.7 | 171.4 | 172.1 | 172.8 | 173.5 | 174.2 |
174.9 |
| 74歳 | 175.6 | 176.3 | 177 | 177.7 | 178.4 | 179.1 | 179.8 | 180.5 | 181.2 | 181.9 | 182.6 | 183.3 |
| 75歳 |
184(以降同じ) |
|||||||||||
申請に必要な書類
世帯構成や年金記録によって必要書類が異なりますので、 あらかじめ市民課年金係へご確認ください。
※代理人の方が申請する場合は、委任状と代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。詳しくは、日本年金機構「窓口での年金相談のご案内」をご覧ください。
請求手続き先
■ 国民年金第1号被保険者の加入期間のみの方:市民課 年金係
■ 国民年金第3号、厚生年金、共済組合等の加入期間がある方:最寄りの年金事務所
詳しくは、日本年金機構「老齢年金の請求手続き」をご覧ください。
お問い合わせ
市民経済部 市民課 年金係
電話番号:098-893-4411(内線 2763 / 2764)
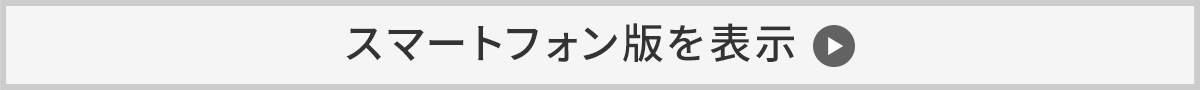






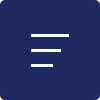
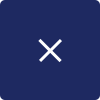

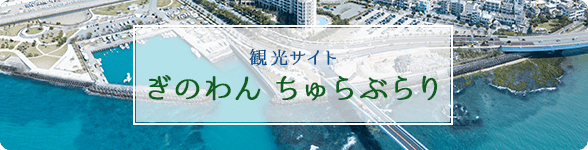


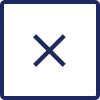









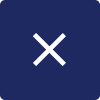
更新日:2025年04月30日