子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)
1.子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)とは
子宮頸がんの原因となるHPV(ヒトパピローマウイルス)の感染を防ぐワクチンです。HPVに感染しても、ほとんどの人ではウイルスが自然に消えますが、一部の人でがんになってしまうことがあります。
海外や日本で行われた調査では、HPVワクチンを導入することにより、子宮頚がんになる手前の状態(前病変)が減るとともに、がんそのものを予防する効果があることもわかっています。
関連サイト
沖縄県HP「子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)」https://www.pref.okinawa.jp/iryokenko/shippeikansensho/1005861/1006410/1006411.html
厚生労働省「HPVワクチンに関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/hpv_qa.html
2.ワクチン接種の効果
HPVの中には子宮頸がんを起こしやすい種類(型)のものがあり、HPVワクチンはこのうち一部の感染を防ぐことができます。
現在、日本国内で使用できるワクチンは、防ぐことができるHPVの種類によって、2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、9価ワクチン(シルガード9)の3種類があります。
令和5(2023)年4月から、シルガード9も定期接種の対象として、公費で受けられるようになりました。シルガード9についての詳細は、「9価HPVワクチン(シルガード9)について」をご覧ください。
サーバリックスおよびガーダシルは、子宮頸がんをおこしやすい種類であるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。
シルガード9は、HPV16型と18型に加え、31型、33型、45型、52型、58型の感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。
3.接種の受け方
1)対象者
小学校6年生~高校1年生相当の女子(宜野湾市に住民票がある方)
|
2)接種期間
高校1年生の3月31日まで
Step1.親子健康手帳(母子健康手帳)にてHPVワクチンの接種履歴を確認。
Step2.実施医療機関へ予約 ※要予約
Step3.接種を受ける際に必要なものを持参し予約した病院へ受診
予防接種は、指定医療機関において実施しています。下記リンクの指定医療機関をご確認の上、接種を受けてください。
注意:一覧に掲載されていない医療機関での接種は原則自己負担になります。
5)接種費用
無料
注意:期限を過ぎた場合や指定医療機関外での接種は全額自己負担となります。
(1回17,000円~30,000円程度/自費の場合)
注意:ワクチンの種類や医療機関によって価格が異なります。
6)接種を受ける際に必要なもの
親子(母子)健康手帳・健康保険証・予診票
注意:接種を希望する際、予診票に保護者の署名が必要です(満16歳以上は本人署名)。また、13歳以上16歳未満の対象者については、事前にご署名をいただくことで保護者の同伴なく接種することができることとなりましたが、急な体調変化をきたす恐れもあるため、保護者の同伴をお願いいたします。
7)予診票ダウンロード
予診票は以下のいずれかの方法で入手できます。
a.予診票をダウンロード印刷しご持参ください。
b.実施医療機関に備え付けております。
(注意)任意接種用の予診票は使用できませんのでご注意ください
(注意)備え付けがない場合もありますのでお電話等で備え付けの予診票があるか確認ください。
8)接種方法
現在、HPVワクチンは2価ワクチンと4価ワクチンと9価ワクチンの3種類があり、原則、同じ種類のワクチンを3回接種します。ワクチンによって接種間隔が異なります。
〇サーバリックス(2価)について
【標準的な接種間隔】
・1回目接種後、1か月あけて2回目、1回目から6か月あけて3回目(合計3回)
【最短での接種】
1回目接種後、1か月以上あけて2回目、1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上あけて3回目(合計3回)
〇ガーダシル(4価)について
【標準的な接種間隔】
・1回目接種後、2か月あけて2回目、1回目から6か月あけて3回目(合計3回)
【最短での接種】
1回目接種後、1か月以上あけて2回目、2回目から3か月以上あけて3回目(合計3回)
〇シルガード9(9価)について
★1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合
【標準的な接種間隔】
1回目接種後、6カ月あけて2回目(合計2回)
【最短での接種】
1回目接種後、5カ月以上あけて2回目(合計2回)
注意:1回目から2回目の接種間隔が5か月未満である場合は、3回の接種が必要となります。
注意:2価及び4価のHPVワクチンとの交互接種となる場合は3回接種となります。
★1回目の接種を15歳になってから受ける場合
【標準的な接種間隔】
1回目接種後、2か月あけて2回目、1回目から6か月あけて3回目(合計3回)
【最短での接種】
1回目接種後、1か月以上あけて2回目、2回目から3か月以上あけて3回目(合計3回)
4.接種後に現れる可能性のある症状
子宮頸がんワクチン接種後にみられる主な副反応として、発熱や接種した部位の痛み、腫れ、注射による痛み、恐怖、興奮などをきっかけとした失神などが挙げられます。
【多くの方におこる症状】
・注射した部位の痛み、腫れ、赤み
・疲れた感じ、頭痛、腹痛、筋肉や関節の痛み
【その他の症状】
・注射した部位のかゆみ、出血、不快感
・発熱、めまい
・発しん、じんましん
・緊張や不安、痛みなどをきっかけに気を失う
【まれに起こるかもしれない重い症状】
・呼吸困難、じんましんなどを症状とする重いアレルギー(アナフィラキシー)
・手足の力が入りにくいなどの症状(ギラン・バレー症候群)
・頭痛、嘔吐、意識の低下などの症状(急性散在性脳脊髄炎)
接種後に体調の変化や気になる症状が現れたら、接種を行った医師・かかりつけの医師、HPVワクチン接種後に生じた症状の診療に関する協力医療機関へご相談ください。
5.子宮頸がん予防ワクチンに関する相談先一覧
厚生労働省の相談窓口
HPVを含む予防接種、その他感染症全般についての相談を受け付けています。
- 電話番号 0120-995-956
- 受付日時 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始除く)
沖縄県の相談窓口
【医療、救済等に関すること】
沖縄県保健医療介護部地域保健課 感染症対策班:098-866-2215
【学校生活に関すること】
沖縄県教育庁保健体育課健康体育班:098-866-2726
【協力医療機関】
HPVワクチンの予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関が各都道府県に設置されています。
沖縄県の協力病院 : 琉球大学病院(麻酔科)098-895-3331
健康被害救済制度について
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市により、給付が行われます。
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)
この記事に関するお問い合わせ先
健康増進課 予防係
〒901-2215
沖縄県宜野湾市真栄原1-13-15
電話番号:098-898-5596
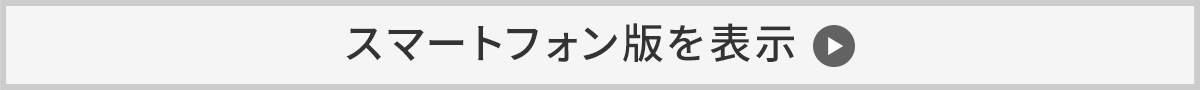






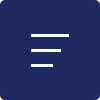
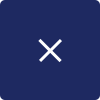

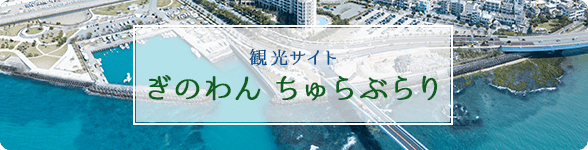


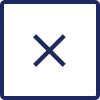









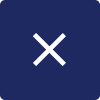



更新日:2025年05月29日