令和7年度宜野湾市認可外保育施設等の施設等利用給付認定(保育料無償化)について
令和7年4月1日以降の施設等利用給付認定(保育料無償化)についてのご案内
認可外保育施設等の施設等利用給付認定(※以下、保育料無償化と記載。)は、保護者様が必要な書類を宜野湾市役所子育て支援課に提出して以降について行います。
【提出期限】令和7年3月31日(月曜日)まで
※4月2日以降に申請された場合は原則申請日からの認定となります。遡及して認定は行わないため、お早めにお手続きください。
※留意事項(1):児童1名あたり1件の申請が必要になります。他のきょうだいが認定済みであっても、別の児童で新規認定を行うためには申請が必要となります。
※留意事項(2):宜野湾市から他市町村へ転出された場合は、宜野湾市での無償化認定を取り消すことになります。引き続き無償化認定を受けるためには、転出先の市町村にて無償化認定申請手続きを行ってください。原則、申請日からの認定となり、遡及して給付することはできませんので、転出先の市町村にてすぐに無償化申請をするようにお願いいたします。
※留意事項(3):当制度(施設等利用給付認定)は「認可保育施設」や「企業主導型保育事業所」の保育料無償化とは異なりますので、ご注意ください。
【郵送で提出する際の宛先】
〒901-2710
宜野湾市野嵩1丁目1番1号 宜野湾市役所 子育て支援課
【お問合せ先】
宜野湾市役所 子育て支援課 電話番号:098-893-4156(直通)
保育料無償化の概要
保護者様の無償化認定要件
令和7年4月1日時点3歳以上の場合(新2号認定)
保護者様について、就労等の「保育を必要とする事由(家庭保育が出来ない理由)」が必要になります。下記の「保育料無償化の申請書に添付する、保育を必要とする事由書類」をご覧になり、該当する書類をご提出ください。
令和7年4月1日時点2歳以下の場合(新3号認定)
(1)「保育を必要とする事由」に加えて、(2)住民税非課税世帯であることも要件となります。
令和7年4月から8月までの認定は、令和6年度税情報に基づいて判定いたします。
令和7年9月から令和8年3月までの認定は、令和7年度税情報に基づいて判定いたします。
市が税情報を把握できない場合には、所得課税証明書等をご提出いただき、市が判定いたします。
無償化の上限額(月額)について
【市が無償化対象としている以下の施設やサービスをご利用の場合】
〇認可外保育施設 〇病児保育事業 〇ファミリーサポートセンター
〇一時預かり事業 〇ベビーシッター
■新2号認定(令和7年度3歳児クラス以上)の方:月額37,000円が上限となります。
■新3号認定(令和7年度2歳児クラス以下)の方:月額42,000円が上限となります。
【公立幼稚園・新制度移行幼稚園・認定こども園の預かり保育事業をご利用の場合】
■新2号認定又は新3号認定の方:利用日数×450円
※新2号認定の方は月額11,300円が上限となります。
※新3号認定の方は月額16,300円が上限となります。
※『大山こども園』は無償化対象外となります。
【従来型の幼稚園(新制度未移行幼稚園)をご利用の場合】
■新1号認定(午前保育のみ)の方:月額25,700円が上限となります。
■新2号認定又は新3号認定(午前保育と午後預かり)の方:
(午前保育部分)は月額25,700円が上限となります。
(午後預かり部分)について、新2号認定の方は月額11,300円、新3号認定の方は月額16,300円が上限となります。
※留意事項(1):上限額を超える分の保育料は保護者負担になります。
※留意事項(2):無償化の対象となるのは保育料及び新制度未移行幼稚園の入園料です。教材費・行事費・給食費・送迎費等は保護者負担となります。
※留意事項(3):幼稚園・認定こども園を利用されている方は原則として、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター、ベビーシッターは無償化対象外となります。
※留意事項(4):認定開始日及び終了日が月途中の場合は上限額が日割り計算となります。
保護者様から市への保育料等請求手続きについて
請求手続きの方法は以下の2つになりますが、保育施設によって異なります。どちらの方法になるかは利用している保育施設にご確認ください。
■法定代理受領:保育施設等が保護者様に代わり無償化対象となる保育料を宜野湾市に請求いたします。そのため、保護者様は上限額の範囲内で保育料の支払いが不要になります。
■個人償還払い:保護者様自身で以下の書類を揃えて、子育て支援課窓口にて請求手続きが必要です。
(1)領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書(※保育施設側が発行した原本)
(2)窓口来庁保護者の身分証明書
(3)振込先の預金通帳又はキャッシュカード
※留意事項(1):保護者様は利用月の翌月以降から償還払いの手続きが可能になります。
※留意事項(2):保護者様の請求期限は利用月の翌月初日から起算して2年間です。
※留意事項(3):認定保護者様と別の口座名義に振り込む場合は委任状が必要です。
【無償化に関する各担当窓口】
■認可外保育施設等の無償化申請・認定について
子育て支援課 保育児童係 電話番号:098-893-4156(直通)
■幼稚園・認定こども園の無償化申請・認定について
子育て支援課 保育児童係・幼保支援係 電話番号:098-893-4156(直通)
■保育料等の請求手続きについて
子育て支援課 幼保支援係 電話番号:098-893-4649(直通)
対象となる施設等
宜野湾市内で対象となる施設やサービスについては、下記のPDFファイル「宜野湾市の認可外保育施設等一覧(令和7年4月時点)」からご確認ください。また、市外の施設やサービスを利用する際は、施設や施設所在市町村役場にご確認ください。
宜野湾市の認可外保育施設等一覧(令和7年4月時点) (PDFファイル: 406.7KB)
※留意事項(1):無償化の対象となる認可外保育施設は、認可外保育施設指導監督基準を満たすことが必要になりますが、無償化が開始された令和元年10月1日より5年間(令和6年9月30日まで)は経過措置期間として、基準を満たしていない場合でも無償化の対象としておりました。経過措置期間終了に伴い、令和6年10月1日以降、指導監督基準を満たさない認可外保育施設は無償化の対象外となり、保育料は全額自己負担となります。市内の認可外保育施設が指導監督基準を満たしているかどうかは、上記のPDFファイル「宜野湾市の認可外保育施設等一覧(令和7年4月時点)」からご確認いただけます。
(1)保育料無償化の申請書(※提出必須)
PDF形式とエクセル形式いずれかをご利用ください。
※留意事項(1):児童1名あたり1件の申請が必要になります。他のきょうだいが認定済みであっても、別の児童で新規認定を行うためには申請が必要となります。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(兼現況届) (PDFファイル: 633.0KB)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(兼現況届) (Excelファイル: 30.6KB)
(2)保育料無償化の申請書に添付する、保育を必要とする事由書類 (※保護者様それぞれが当てはまるものを提出)
以下の1~9に該当する保護者様それぞれの「保育を必要とする事由」を証明する書類をご提出ください。きょうだいがいる場合、どちらかはコピーで対応可能です。
1.就労の方
■就労(申告)証明書(子育て支援課指定の様式)
■自営業や法人役員等の場合、就労(申告)証明書に加えて、官公庁が発行した証明書(又は官公庁に提出した届出書等)の写し
(注)保護者の氏名が記載されているものに限る。
【提出が必要な添付書類の例】
(1)令和6年1月1日以前から自営業を開始している方:
■税務署等で確定申告をした際の本人控えの写し
(注)原本には官公署の受付印が必要となります。
(注)e-taxで申告している場合には送信日時が記載されたページをご提出ください。
(2)令和6年1月1日以降に自営業を開始した方:
■税務署へ提出した個人事業開業届の本人控えの写し
(注)原本には官公署の受付印が必要となります。
■保健所が発行した営業許可証等の写し
(3)法人役員の方:
■ご自身の住所・氏名が記載された法人登記簿謄本の写し
(注)6カ月以内に発行されたもの
(4)家族従事者・協力者の方:
■民生委員からの証明
(注)上記の『自営業を証明する書類』をいずれも提出できない場合には、原則として認定できませんが、他に自営業をしていることが確認できる資料を提出いただけた場合には、審査の上で認定することがあります。
就労(申告)証明書(両面印刷) (PDFファイル: 274.6KB)
就労(申告)証明書(両面印刷) (Excelファイル: 128.4KB)
就労(申告)証明書記載例:被雇用者または法人役員(片面印刷) (PDFファイル: 216.8KB)
就労(申告)証明書記載例:自営業(片面印刷) (PDFファイル: 224.9KB)
就労(申告)証明書(両面印刷)Certificate of employyee English version (PDFファイル: 168.1KB)
就労(申告)証明書(両面印刷)Certificate of employyee English version (Excelファイル: 69.7KB)
※家族従事者・協力者の方について、民生委員から証明を受ける際は、以下の書類を担当民生委員にご提出ください。
■民生委員への依頼書(子育て支援課指定の様式)
民生委員への依頼書(両面印刷) (PDFファイル: 125.8KB)
民生委員への依頼書(両面印刷) (Excelファイル: 22.0KB)
2.妊娠・出産(予定)の方
■親子健康手帳(母子手帳)の写し
(注)親子健康手帳(母子手帳)のうち、表紙等の保護者氏名が記載されたページと分娩予定日が記載されたページの写しをご提出ください。
(注)就労先に在籍したまま、産前・産後休暇または育児休業を取得している(取得予定)の方は就労(申告)証明書をご提出ください。
3.疾病・障がいをお持ちの方
■以下のいずれかをご提出ください。
(1)診断書(子育て支援課指定の様式)
(2)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳いずれかの写し
4.親族の看護・介護をしている方
■看護・介護申立書(子育て支援課指定の様式)
■看護・介護申立書に加えて、以下のいずれかをご提出ください。
(1)診断書(子育て支援課指定の様式)
(2)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、介護保険被保険者証いずれかの写し
(注)2について、介護保険被保険者証は要介護認定の場合に限ります。
看護・介護申立書(両面印刷) (PDFファイル: 210.6KB)
看護・介護申立書(両面印刷) (Excelファイル: 27.4KB)
5.災害復旧の方
■罹災証明書
6.求職活動の方
■求職活動状況申立書(子育て支援課指定の様式)
(注)求職活動を理由に在園できるのは、退職日の翌日から起算して90日後の月末までになります。
求職活動状況申立書(両面印刷) (PDFファイル: 133.5KB)
求職活動状況申立書(両面印刷) (Excelファイル: 21.8KB)
7.就学の方
■学校が発行した以下の(1)と(2)の両方が証明できる書類をご提出ください。ただし、通信制で時間割等の授業日程を証明できる書類が無い場合は(2)の代わりに(3)を提出してください。
(1)在学証明書等の在学期間(入学日と卒業予定日)が証明できる書類
(2)時間割等の授業日程を証明できる書類
(3)授業(学習)日程申立書(子育て支援課指定の様式)
授業(学習)日程申立書(両面印刷) (PDFファイル: 203.4KB)
授業(学習)日程申立書(両面印刷) (Excelファイル: 25.3KB)
8.育児休業の方
■就労(申告)証明書(子育て支援課指定の様式)
(注)産前・産後休暇及び育児休業期間、職場復帰予定日の記載が必要になります。
(注)育児休業前から認可外保育施設等を利用しており、引き続き育児休業を取得する必要があると認められるときに限ります。
(注)育児休業の認定有効期間は、育児に係る児童(下のきょうだい)が2歳になった日が属する月の末日までになります。
9.みなし育休の方
■継続利用に関する申立書(子育て支援課指定の様式)
(注)みなし育休の認定を受ける前から認可外保育施設等を利用しており、出生したきょうだいの家庭保育を引き続き行うことが必要であると認められるときに限ります。
(注)みなし育休の認定有効期間は、みなし育児に係る児童(下のきょうだい)が2歳になった日が属する月の末日までになります。
継続利用に関する申立書(両面印刷) (PDFファイル: 118.8KB)
継続利用に関する申立書(両面印刷) (Excelファイル: 20.1KB)
(3)該当する世帯のみ必要な書類
以下の世帯に該当する方はご確認ください。
ひとり親世帯(※離婚や別居予定も含む)
(1)児童扶養手当又は母子・父子家庭等医療費助成を受給されている方
■関係部署へ受給状況を照会させていただくため、受給証書等の提出は不要です。
(2)遺族年金を受給されている方
■遺族年金の受給を確認できる年金証書の写し
(3)上記の(1)と(2)いずれも受給していない方
■戸籍謄本の写し
(注)保護者と児童の戸籍が別々の場合はそれぞれの戸籍謄本の写しが必要になります。また、受付日から起算して6カ月以内に発行されたものであることが必要です。
(4)家庭裁判所で離婚に向けて調定・裁判中の方
■家庭裁判所が発行した事件係属証明書の写し
■児童相談所が発行した措置決定通知書等
保護者様が軍人・軍属の方
■2023年(令和5年)中の収入を証明する書類(W-2 2023)
※児童の学齢が令和7年4月1日時点で0~2歳児(新3号認定対象)の方は提出が必須となります。提出がない場合、令和7年4月1日以降の認定ができません。
(注)ただし、児童の学齢が令和7年4月1日時点で3歳児以上であれば提出不要となります。
(注)上記書類(W-2 2023)の提出をする必要がある保護者について、令和7年6月27日(金曜日)までに「W-2 2024」の提出をして下さい。提出がない場合、令和7年9月1日以降の認定ができません。また、提出して頂く「W-2 2024」の内容が課税世帯同様であった場合は、令和7年8月31日を以て新3号認定は取消となります。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 保育児童係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4156
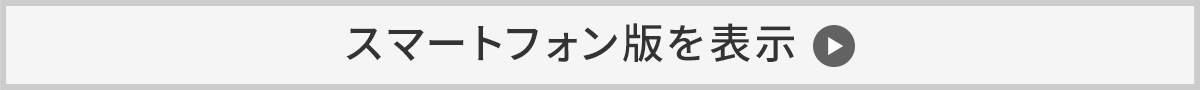






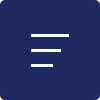
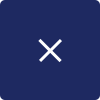

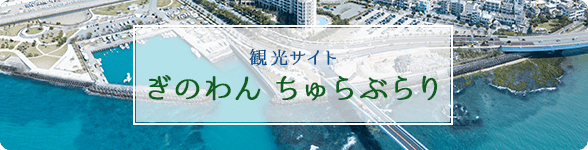


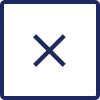









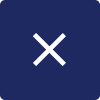
更新日:2025年04月10日