認知症高齢者の扱いに対する自治体の考え方、今後のスタンスをお聞かせください
投稿内容
最初に申し上げておきますが、地域包括支援センターぎのわんへ(以下ぎのわん)は3回ほど相談済みです。私自身、グループホームで仕事をしています。その上できれいごとではなく、今後認知症高齢者に対する自治体としての方針やスタンスをお聞かせ願いたいです。
ここ数年、私の自宅を訪ねてくる高齢者の方がおり、明らかに過去の断片的な記憶との混同によりここにいない人を探して訪ねてきています(私自身、本人から聞き取りもしています)。介護施設では普通に見られる方ですが、一般の方からは異常者のようにしか見えないでしょう。その方の訪問頻度もここにきて頻回になっています(週4回のデイケア以外の日はほぼ訪ねてきており、今日にいたっては朝7時から10時まで一時間おきにインターホン、ノック、本人荷物持参)。認知症はどんどん進行していくものですし、また治るものでもありません。そういったことを私も熟知しているので、これらを踏まえた上で窓口のぎのわんに相談しています。最早、私だけの問題ではなくなりつつあり、近隣住民も不安と恐怖を覚えてもおかしくない状況になっています。しかし、相談したところですぐに解決する問題でもなく、また動いてくれてはいるのでしょうが、ケアマネージャーも現状の制度で30人担当しているなど全てをこの方に神経注ぎ込むわけにもいかないでしょう。この話については、直接介護長寿化へ相談するつもりではないので、これ以上は申し上げませんが、現状、認知症高齢者に関するこの手の話が急速に増えてきているのではないですか?市はどの程度把握できていますか?そしてその問題に対して現状何がどの程度不足しているのか、予算は、法整備はなどどれだけ課題をあげて市は取り組んでおられるのでしょうか?現在起きている事象は認知理解している以上に深刻になっているように思います。現状のシステムで間に合っているのでしょうか?それとも、子供が少ない以上先細りとみて、このまま何もせず我関せずで先送りするつもりでしょうか?自分たちの世代の危機が迫っているのに。まさか、下部組織へ委託委任しているから自治体は関知しないということはないと思いますが。
自分の親の最後までついに顔を見せなかった家族の話や、徘徊する高齢者の方の先を案じ安全設備の導入や施設入居を奨めているにも関わらず後見人が承諾せず、ついぞ話が進まないという事もかなりあるのではないですか?人間生まれてから死ぬまでが人間です。他人事ではないです。現状介護従事者の不足も深刻な問題ですが、その点の将来的なことはどのようにお考えですか?昨今の高齢者に対する世の中の不当な風潮(老害という言葉、高齢者が起こした事故の報道での取り上げ方など)に対してはどうお考えですか?
ここまで、かなり長々とたくさんの事を書いてきたので、お聞かせ願いたいと申しましたが、難しいようであれば無理に回答していただかなくても結構です。むしろ、上に報告させていただきますなどの具体性のない回答では意味がないので不要です。ただ、定期的に発行されている宜野湾市の市報やホームページで改善したことなどを取り上げていくことはできるはずなので、そちらで大々的に取り上げていっていただきたいです。行政の限られた人数ではアイデア不足でもあると思うので、介護施設などからも意見を吸い上げ実際に実行していってほしいです。
回答
この度は、貴重なご意見ありがとうございます。ご投稿頂きました件につきまして、介護長寿課より回答いたします。
投稿者様のご自宅を訪ねていると思われる高齢者につきまして、当事者へのご対応及び地域包括支援センターへご連絡していただき、誠に感謝申し上げます。ご投稿いただきました件も含め、関係機関(地域包括支援センターぎのわん、宜野湾市社会福祉協議会 等)と情報共有および連携を図り、当事者の見守りや今後の対応について協議を進めております。
また、認知症高齢者の把握状況についてですが、多様な問題を抱えた方等については高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターから介護長寿課へ情報共有を受け、必要に応じて関係機関の支援につなぐ、会議の場を設けて課題解決に向けた協議を行うなどの対応を行っております。
しかしながら、実際には介護保険サービスや地域資源のみでは課題解決に至らないケースもあり、地域支援事業における柔軟なサービスの創設、生活支援体制整備事業を通した地域づくり等、地域の実情に合わせた工夫が必要であると考えております。
今後、関係機関だけでなく地域住民や介護施設等からのご意見を賜りながら、多様な高齢者の課題解決につながる方法を増やしていけるよう努めてまいります。
また、法的には「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が令和6年1月1日より施行され、第三章 基本的施策の中に“認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進”、“認知症の人の社会参加の機会の確保等”が含まれており、今後さらに認知症高齢者が地域で暮らし続けられる社会となることが求められております。本市としましても、認知症基本法の趣旨に沿った地域づくりができるよう努めてまいります。
認知症に関する取り組みの周知についても、引き続き継続してまいります。
今後とも本市の高齢者保健福祉行政へのご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
問い合わせ
介護長寿課 長寿支援係(内線:4139)
この記事に関するお問い合わせ先
秘書広報課
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4411
秘書広報係:内線2411
秘書係:内線2000、2001
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
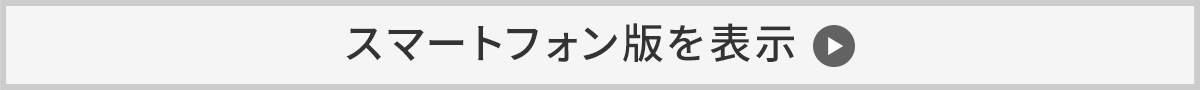






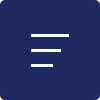
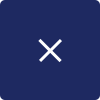

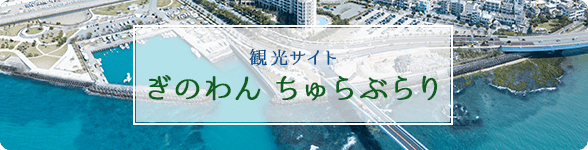


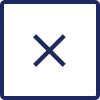









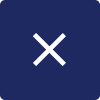
更新日:2024年12月04日