今日の文化課 2024年9月
9月30日 【あの有名なベーカリーショップの工場が我如古に!?】
現在絶賛開催中の「イガルー・シマ文化財教室」では、毎度受講生からの鋭い質問に感銘も受けつつ我々も学びになっています(^^)
先日取り上げた「ドーダガー」および「チブガーラ」に関しても、質問を受けて深堀調査を開始しました♪
そんな作業のなか、志真志~我如古に面白い発見があったのでご紹介を(^^)
チブガーラ(志真志ガーラ)を年代を追って追いかけてみていたところ、
40年ほど前の写真に写る、川沿い(写真上部の緑のライン)には何やら聞き慣れた名前の大きな工場が??

(写真:国土地理院)
中央のグラウンドが見える学校は中部商業です。330もまだ浦添側は開通していません(^^;
その工場の屋根の上には「ジローパン」!?
え?これってあれですよね? あの「ジローベーカリー」の工場ですよね!? 色々調べてみたもののまだ確証は持てていないのですが、おそらくそうだと思います(^^)

ベーカリーショップ自体は喜友名にありましたよね、
屋上に小さい観覧車が写った写真なども有名な「フォートジロービル」!
聞くとこによると、ビル内にはスケート場やボーリング場もあったとか!?
今でいうラウンドワン状態!?
そのジローベーカリーの工場が我如古にあったんですね!
しかも見るからに大工場!
そしてその工場跡が今何になっているか分かりますか(^^)
我如古交差点あたりの330号線からチラッと見えるので、気になってる方も多いでしょう♪
そう、なんとあの首里城の唐玻豊を思わせる立派な造りのお寺さんです!

面白いですよね~♪
ジローベーカリーは残念ながら閉店してしまったようですが、戦後沖縄の歴史においてすごい存在感を示してくれたベーカリーだったと思います(^^)
ジローさんこと照屋次郎さんは、「普天間でいご通り」(現ヒルズ通り)の名付け親でもあるそうです。失われた宜野湾並松の再現とばかりに、地元と協力して喜友名から普天間までの通りにでいごの木を400本も植樹したことに由来するのだとか♪ (参照:島ネタCHOSA班)
ベーカリー工場時代のことを知ってる方がいれば、ぜひ情報いただきたいのと、懐かしいと思ってもらえる世代にはぜひぜひ写真を見せてあげてみてくださいね♪
9月27日 【琉大近くのドーダガーってどーだばー?】
先日、イガルー・シマ文化財教室で出た質問の答え探しに、とある場所へ訪れてきました。
さてどこでしょう(^^)?
イモの葉っぱよ、それ「カンダバー」
ヨモギの葉っぱよ、それ「ふーちばー」
え、なんだわけそれ?「なんだばー?」
WBC活躍の日系メジャーリーガーよ、それ「ヌートバー」
ぬーいっとんばー。
おふざけはこのくらいにして(^^;
今回訪れたのは
琉球大学近く(敷地内?)の「ドーダガー」という湧水!
(執筆者はアナタの想像通りの年齢です。。)
以前にもお伝えしてると思いますが、ウチナーグチで湧水のことを「カー」とか「ガー」とかと呼びます。
なので、ドーダガーはドーダのカーのことなんですね♪
って、それはいいとして「ドーダ」って一体なに(^^;?
これドーダ!? しつこい(^^;
実は、現西原町の「道田原(ドウダバル)」という小字にあるカーなので「ドーダガー」と呼ばれているんです。
この泉から湧き出て出来た小川が「チブガーラ」(カーラは「川」の意)で、近年川辺にオクラレルカを育て地域活性を行っていることでも話題になっているあの小川です♪
こちらのチブガーラや長田を流れる川が、長田の地形、もっと言えば宜野湾の屋取集落の特徴的な地形にも大きく関わってくるのです♪
そのことを知って330号線や市道11号線を走ってみると、きっとほほ~!と唸りますよ(^^)!
そのあたりはまた次回に♪ 興味ある方はイガルー・シマ文化財教室への参加も待ってます(^^)
ドーダガー近くの高速道路上を渡る橋の名前にも「道田橋」、「チブガーラ橋」と名付けられていますので、探してみてくださいね♪
9月26日 【我如古ヒージャーガー 今しばらくご注意願います】
先週の台風後の文化財パトロールにて、我如古ヒージャーガーの倒木の心配がなくなったので見学が再び可能となりました!とお伝えしましたが、
本日に本格的な清掃を行うため訪れてみると、
なんととと、
コンクリートブロックくらいの大きさの木の欠片がいくつか落ちてきていました(;;)
ただ、内部がスカスカにはなっていたので、すでにだいぶ弱ってた上に前回の台風の強風で(台風去った後に風強まりましたよね^^;)落ちてきたんだと思われます。
大がかりの剪定を行った直後なので、若干このような弱った木の欠片がまだ落ちてくることも考えられなくはありません。
ということで、今後しばらくは立ち入り禁止とまではいかないまでも、みなさん、見学や通行の際には十分に十分すぎるほどの注意をお願いします。
9月25日 歴史の道を訪ね歩く Vol.7【大謝名に鉄道駅?】
久しぶりに歴史の道シリーズへ戻ってきました(^^;!
日々いろいろ起こりますのでね(^^; あっちゃあっちゃーしながら歴史の道も伝えていきたいと思います。
さて、前回は大謝名のジャナマガヤー~軽便鉄道トンネル~宇地泊のキャンプブーンあたりまでをお話ししましたが、ジャナマガヤーのちょうど向かい側に大謝名の集落が広がっていました。
そしてジャナマガヤーから大謝名集落にかけては、集落へ入って行く道1と、集落の側を通って北向けのフルミチに上っていく道2との2つの道がありました。

(写真:国土地理院)
実はこのどちらがかつての中頭方西海道だったのかははっきりと分かってはいないのですが、今回は集落へ入っていく道1を紹介しましょう♪
浦添方面から、かつてのジャナマガヤーへ曲がる道(ガソリンスタンドとローソンの間)の反対側、58号線をまたいだ向かい側に結構な角度で進入する小道があります。自動車屋さんと背の高いビルの間の道です。
この道が上の航空写真でも見える道1です。
58号線から眺めるとよく分かるのですが、結構な勾配もあるのです。
そう、この勾配こそが!かつてそこに軽便鉄道が通るためのトンネルがあった高低差をイメージさせてくれます♪
この道を下りていくと小さな交差点があり、右方向は大謝名団地へ、真っすぐは大謝名小学校や大謝名集落へと向かいます。
大謝名団地へ向かう道は、その先の宇地泊川(比屋良川)も渡り牧港川も渡るのですが、実はこの道にかつての軽便鉄道の線路があったんです♪
さらに、団地方向へ100mほど進んだあたりには「大謝名駅」があったとされます!

↑団地側から見た写真。右手の店舗跡あたりに駅があったようです。左手は丘陵になっていて(ワイトゥイか?)、ここにも高低差の名残を感じることができます。
軽便鉄道は、この道を真っすぐ大謝名交差点に向かいトンネルをくぐっていたようです。今では突き当りに住宅が立ち並び、通り抜けていた様子を窺い知ることは難しいですが(^^;
と、先ほどの交差点に戻って、今度は大謝名小学校向けに歩きましょう。交差点すぐのところには宇地泊のウブガー「クンカー」(湧水)が見えます。
こちらのクンカーにちなんで、集落へ入っていくこの道を「クンカーミチ」とも呼んでいたようです。
と!本日はこのあたりまで(^^)
ぜひ実際に足を運んで、歴史の道ロマンを感じてみてくださいね♪
9月24日 【喜友名泉見学同行!湧水ファン増やし隊!】
先週の金曜日午後になりますが、喜友名泉の見学依頼があって、県内在住のお二人を連れて見学に行ってきましたよ(^^)
(台風の影響か、珍しく水が濁って水位も高くなっていました)
実は同じ日に県外からも喜友名泉を見学をしたいとの依頼が入っていたのですが、台風の影響なのか沖縄入りすることすら出来なくなってしまったとキャンセルの一報もあったのでした。
私どもとしても、文化財に興味を持ってもらえることほど嬉しいことはないので(^^) みなさんもお気軽に見学依頼をされてくださいね♪ 希望日一週間前までに連絡を頂けるようお願いします。
基本平日の9:00~16:00 とさせて頂いていますが、場合によっては都合を付けられることもありますので(^^)
今回見学されたお二人は県内の文化財に興味をお持ちとのことで、各地いろいろまわられているようです。それでも喜友名泉にはとても感動してくれた様子で、しきりに「すごい~!上等~!」と唸ってくれていました(^^)
喜友名の他の文化財にも興味を持ってくれたようで、石獅子群巡りにも歴史の道歩きにも興味津々の様子でした♪
それから見学前の金曜午前中は、宜野湾在住の方であれば一度は名前を聞いたことあると思います宜野湾名士「仲村元惟」先生との打ち合わせを行ってきました。
というのも、次回のイガルー・シマ文化財教室は真栄原・佐真下の屋取をテーマに、元惟先生に「真栄原・佐真下よもやま話」を御講話いただくことになっているからです(^^)
打ち合わせとはいうものの、我々自身もすごく勉強になるお話を聞かせてもらいました♪
次回のイガルー・シマ文化財教室は10月5日(土曜)10:00~12:00 真栄原公民館にて開催です。
皆さんのご参加お待ちしておりまーす!
9月19日 【台風前後の文化財パトロール】
今年は沖縄に台風来ないね~と言ってたら、一気に二週連続でやってきましたね(^^;
しかし、台風の進路が沖縄寄りでなく本土へ集中したり、日本を縦断するように北上したり、これも気候変動なのかな~と思ったころに沖縄にやってきた台風の影響も小さかったこと(^^;
「大型の台風直撃」って前触れに、県民のみなさん結構な対策したと思いますが、あれ?いつ通った?くらいの影響でしたね(^^;
まぁ、備えあればということですし、大陸の方に上陸してから猛威を振るったようにも見えますよね。やはり地球規模で何か変化が起こっているのでしょうか。
さて、そんな台風の季節、文化課では文化財を台風から護るための対策、台風が過ぎ去ったあとの見回りも大事な作業となってきます。
今回の台風は前述したように雨風もそんなに強くなく、ちょっと木の枝が落ちてきてるかなーとか、逆に草葉が飛ばされて綺麗になってるかも(^^; なんて場所もあったりで。
何事も起こることなく台風が過ぎ去っていきました(^^)
まだまだ10月末くらいまで安心はできないですが。
とりあえず無事の報告でした~♪
そうそう、それと報告遅れになってしまっていましたが、昨年の大型台風の影響で倒木の危険があり立ち入り禁止となっていた「我如古ヒージャーガー」が、職人も職人の剪定士の作業により危険枝木が除去されまして、ようやく先月から通行可能となっています♪
今回のパトロールでも、小枝が少し落ちてはいましたが危険は除去されていることを確認できました(^^)
雨の影響で水量も豊富!まだまだ暑さの残る沖縄での癒しになりますよ♪
ぜひ訪れてみてくださいね♪
場所は我如古公民館の裏側になります。
9月18日 【宜野湾市第29号目の文化財誕生!】
宜野湾市にはこれまで、28の指定および登録文化財が登録されていましたが、
このたび第29番目(登録文化財としては第3号目)の文化財が誕生しました!
それは~
登録名「喜友名グスク香炉群」と称されます、喜友名にて古来より大切に継承され続けてきた喜友名に纏わる貴重な香炉の数々!
総数16基の香炉が一つの文化財として登録されました(^^)
喜友名では「喜友名の石獅子群」も市の有形民俗文化財として登録されていますし、「喜友名泉(チュンナーガー)」は国指定有形文化財ですからね!
今後より喜友名の歴史散策の楽しみが増えますね(^^)♪
さて、一体その「喜友名グスク香炉群」はどこにあるのか?
現在はパイプライン沿いの喜友名のお宮という祠の中に祀られています。
ただ、今後は場所移動することが予定されており、その移設先が現在整備真っ最中の西普天間住宅地区の公園敷地内となっています!

そうなるとますます雰囲気も固まりますし、訪れることがより楽しみになってくると思います。
では、なぜ移す計画があるのか?
実はここにこそ、今回文化財登録に至った大きな要因も秘められていたんですね。
「喜友名グスク香炉群」と称されることから、グスクに関連した香炉だったんだろうということは想像できると思います。
しかし、そもそも喜友名グスクって何??って思ってしまいますよね(^^;
喜友名にグスクなんてあったの? はい、あったんです(^^)!
その場所こそも!まさに西普天間住宅地区跡地。県道81号線喜友名バス停から普天間にかけてのフェンス境あたりにあったと言われています。
戦後米軍に土地を接収され、ハウジング建設のために破壊されたグスクなのです。
戦前生まれの方々からはハッキリとその存在を聞き取ることができていますし、伝承として喜友名グスクと北谷グスク(イチグスク)との闘いがあったことも伝わっています。
喜友名グスクがあったとされるあたりからは、その大部分を削られてしまった今なお、北谷グスクの様子をはっきりと目にすることができます。

街づくりが完了したあとはフェンスも取り払われ、伊佐~(安仁屋含め)北谷一体を見渡すことのできる、かなりの眺望が期待できる場所になると思いますよ♪
さて話をもどしまして、その喜友名グスクには琉球国の正史にも書き記されている御嶽や殿、火の神がありました。喜友名の人々が古来よりこれらの拝所をことあるたびに拝んでいたことは容易く想像できますよね。
また、グスク近くにはフトゥキアブと呼ばれるガマもあり(現存)、昔から地元の方々の祈りの場となっていました。そこにもいくつか香炉があったようです。
米軍土地接収に伴い、民政府から香炉撤去の通知があり、香炉をやむなく現在のお宮へ移し合祀。その後はお宮を拝所としてウマチー行事などを行ってきました。
しかしこのたび西普天間住宅地区返還に伴い、グスクがあった場所、そしてフトゥキアブも返還地対象エリア内となっていて、そうであるならば香炉たちを元の場所へ戻したい!
そう思われるのは当然の流れですよね(^^)
そこで元のエリア(公園予定地内)に戻す場合の諸条件をクリアしていくために、香炉群の文化財登録を目指し、区が先頭に立って市がそのバックアップを進めていく方向がベストだということになり、長年にわたる諸々の作業を経て今回無事に登録を果たせることとなりました(^^)
本日、その交付式が行われたんですよ♪
宜野湾市教育委員会にて教育長より喜友名区会長へ(^^)
公園が整備されるまでにはまだ時間がかかりますが、その間に進められる状況なども更新していきますね(^^)
9月17日 【台風去って台風前の八月十五夜】
台風連休明けのウチナーからこんにちは(^^)
とはいっても、まったく台風の影響を感じないただただ蒸し暑いだけの週末でしたね(^^;
さまざまなイベントもキャンセルを余儀なくされたものの、実際は普段よりもいい天気なくらいで、残念に思われた方も多々おられたことだと思います。
そこにきて連休明けにはまた次の台風が沖縄に向かっているとか。明日午後あたりに最接近のようですよ(><;
しかし今日は旧暦八月十五日!
中秋の名月、八月十五夜なんです!
昔からこの日は、満月の下で様々な祝い事や伝統行事(ウチチウマチーなど)が行われ、今日も糸満の大綱引きをはじめ、各地で豊年祭やお月見行事が予定されていることだと思います。
今のところ台風の「た」の字も感じさせない快晴にも近い天気で、おそらく今夜は行事を続行される地域が多いのかなと思われますが、早め開催早め収束で(^^; 楽しい十五夜が過ごせればと思います。
また近年では、旧暦の十五夜に合わせると平日開催で都合つかない人が多いため、その日に近い週末にずらして行事を行う地域も増えてきていますよね。
今度の週末あたりにも、各地さまざまに豊年祭・秋祭りなど行われると思うので、ぜひご近所の公民館などへ足を運んでみてください♪
宜野湾市では、大謝名の獅子舞と普天間の獅子舞が「市指定無形民俗文化財」に登録されており、旧暦の八月十五夜、または秋祭りにて披露されますよ(^^)
獅子舞は集落の災厄払い、子孫繁栄、豊年満作を祈願して行われます。
小さいお子さんの頭を獅子に噛んでもらうと健康に育つなんてことも言われたりします(^^;
子供にとってはえらい迷惑な話でしょうけど(^^;
それでは、台風対策を万全に!十五夜の夜を楽しんでください♪
9月12日 【今日は旧暦8月10日 悪霊退散準備はOK?】
今日は旧暦の8月10日となっています。
八月十五夜・中秋の名月まであと数日ですね(^^)
台風の影響が気になるところですが、台風一過の秋の夜長となるといいですね♪
さて、旧盆が終わり、十五夜が近づいているわけですが、昔から沖縄ではこの時期にマジムン・妖怪が出やすくなると言われています。
お盆にご先祖さまと一緒にこの世へ付いて来て、ご先祖様が帰った後もあの世へ戻らずこの世をウロチョロしているんだとか。
そこで、旧暦8月8日は「ヨーカビー」と呼ばれ(妖怪日とも)、爆竹を鳴らして悪霊退散をしていました。今でも行っているところもあるのではないでしょうか。
さらに最もマジムンが出やくなると言われる8月10日から11日(場所によって9日から11日など)には、屋敷に結界を張り巡らせマジムンを寄せ付けないとされる「シバサシ」が行われます。
こちらは今でも見かけること多いのでは(^^)?
宜野湾でもちょくちょく見かけますよ♪
ススキの葉を十字に結って「サン」または「ゲーン」にし、それを家の四隅に挿すことでその内側(屋敷)を守る結界とする。(ススキはその姿から剣をイメージさせ、霊力を持つとされる)

「桑の枝葉」を重ねるとより呪力が高まるんだそう(^^)
桑の木には強力な霊力が宿っており、雷が落ちないと昔から伝わってきました。それで雷が鳴ると人々は「桑原桑原」と唱えたんだそうな。なるほどーですよね!
シバサシの「柴」とは、「雑木の小枝」の意で、その柴を挿すことから「シバサシ」と呼ばれるようです。

サングヮーはその呼称の通り、「サンの小さいやつ」ですね(^^)
今でもお弁当や重箱などの上に置かれているのを見かけますよね♪ お守りとしても見かけるようになりました♪
最近ではあまりススキを見ることも少なくなってきている気もしますが、これを機会にご近所歩いてみて、ススキがあればぜひ「シバサシ」を行ってみてはいかがでしょう(^^)
9月11日 【市立博物館発行の「はくぶつかんネット」が面白い!】
市報ぎのわんを紹介したところで、ぜひ市立博物館発行の「はくぶつかんネット」の紹介も♪

市民の方であれば、一度は行ったことがるかと思います宜野湾市立博物館(^^)
常設展の内容充実度はもちろんのこと、企画展の多さで飽きさせない、すごく清潔感も漂うし職員との距離が近いので気になることも気軽に聞きやすい♪ そしてなにより!入館無料なんですよ!? これは行かない理由はない!

まだ行ったことないという方がいれば明日にでも!そして、あ、しばらく行ってないな~と思った方も明日にでも(^^)!
市民に向けた市民講座も毎月開催していますし、野外講座なんてのも開催しています♪
歴史好きならもう、一気にファンになる!博物館と言ったらじのーん!と言いたくなるくらいの博物館なんです(^^) 市外の方もぜひいらしてください♪
そんな市立博物館が発行する刊行物なので、面白いに決まってる(^^)
今回の7月-10月号(第79号)では、各企画展の様子に加えて、
「普天間満宮の魅力」と題した普天満宮特集を、見開き2ページにも渡って掲載しています!

琉球八社の一つ「普天満宮」
尚賢王が始めたと言われる「普天間参詣」
その参詣道に燦然と連なっていた「じのーん並松」!
普天満宮に伝わる女神伝説の話も紹介されていますよ♪
「はくぶつかんネット」は、博物館はもちろんのこと市役所や図書館でも入手可能です(^^)
ぜひお手にとって読んでみてくださいね♪
バックナンバーもデジタルで読むことできますよ!
9月10日 【市報ぎのわん9月号は文化面特集!?】
「宜野湾歴史の道文化財教室」一般公開解禁!
こちらのブログでも力を入れている、来月から開校する「宜野湾歴史の道文化教室」の一般公開が始まりました!
本日10日付で市報ぎのわん9月号が発刊となりまして、そちらの中で「宜野湾歴史の道文化財教室」の受講申し込み受付情報を掲載しています(^^) <15ページ>

今回はごーやん先生も一緒になって紹介してくれていますよ♪ (ごーやん先生切り抜き保存チャンス!)
それから同号にて第四回「スディバナビラ石畳道文化講座」の申し込み受付内容、
さらにさらに!
これでもか文化課情報!としまして(^^;
同号5ページでは追い打ちをかけるかのように、「ぎのわんの歴史・文化遺産を歩く・其の63」と題して中頭方西海道特集も組んでおります!
写真や絵図も掲載しながら、より分かりやすく紹介しています(しているつもりです^^;)
デジタルデータはこちら
また同ページ上部においては博物館のコラム「茶ぐゎ~ゆんたく」にて、戦後の宜野湾台風対策事情も紹介されていますし、博物館の市民講座募集も掲載されています。
まさに今回は文化特集号といってもいい!?ような内容になっていますので、ぜひぜひ隅から隅まで読んでみてくださいね♪
宜野湾在住の方であれば、本日ご自宅に届いているかと思います。
市外の方で興味持ってくれた方であれば、宜野湾市役所や宜野湾市民図書館などで手に入れることができるので、ぜひ入手してみてくださいね(^^)
歴史の道文化財教室はじめ、各種講座への申し込みもお待ちしておりまーす!
9月9日 【イガルー・シマ文化財教室第二回目は、地質から学ぶ長田と屋取】
去った9月7日土曜日、第二回目のイガルー・シマ文化財教室が長田区公民館にて開催されました(^^)
おかげさまで第一回目を上回る参加者数を数えることができました♪
駐車場も縦列に縦列を重ねたにも関わらず、ほんとあと一台来ると止める場所がない!というほどでした(^^; ただ次回からはまた会場が変わり、少し駐車スペースも余裕が出るかなと思うので、遠慮なく参加されてくださいね!
今回のテーマは「長田の地形と歴史」と題し、沖縄国際大学教授の崎浜先生に講和をお願いしました(^^)
屋取集落がなぜ長田をはじめ宜野湾の東部に多かったのか、宜野湾西部との明らかな地質の違い、それが人々の生活や農作物にどう影響していたのかなどを深く学ぶことができました♪
また、地理学という観点から、宜野湾の土壌性質における防災意識の持ち方、土地を理解するという部分でも受講生の皆さん大いに学ばれていたようです(^^)
今回も質疑応答の時間内に収まらず様々な質問が寄せられていますので、追って紹介できればと思います(^^)
第三回目は10月5日(土曜日)、真栄原区公民館にて宜野湾市の名士「仲村元惟」氏を迎え、屋取集落「真栄原・佐真下のよもやま話」をお話してもらいます♪
次回は少し趣向を変えて、元惟先生と宜野湾市文化財ガイド「察度の会」のメンバーのみなさんとの対話様式も交えてお届けしますよ(^^)
宜野湾市の生き字引と言っても過言ではない元惟先生のお話、ぜひ聞きにいらしてくださいね(^^)
9月6日 【地中から現れた古き石畳に感じる琉球ロマン】
現在、文化課では野嵩スディバナビラ石畳道の確認調査を行っています。
近代における道路整備の際に、古き石畳道と新しく敷かれる道の高低差をなくすために地中へ埋められてしまっていた石畳部分を全面的に検出しました(^^)

(↑草の生えてる部分までは今まで歩けていた石畳道、茶色い部分は今回検出した地中に埋まっていた石畳)
今まで歩けていた石畳部分だけでも古のオーラを感じることのできる、まさに「歴史の道」でしたが、土に埋もれていた石畳を目にすると、より古代へタイムスリップした感が味わえます♪

土嚢のすごい量を見ても、どれくらい掘ったかを分かってもらえると思います(^^;

もしかしたらこの道を護佐丸の息子「盛親」がおぶられながら逃げて、その後「毛氏」が名門中の名門として栄えていったのかなーとかね(^^)
実は今後、調査した部分は再度埋め戻しを行って、より石畳道の雰囲気を味わえるような整備を計画をしています。

ので!こちらの長年土に埋まっていた石畳が見れるのは、
今でしょ!(いまどき言う人いる!? ひまでしょ!)
いや、ほんと今だけになると思われるので、ぜひ宜野湾歴史ファンのみなさま!
早めに足を運んで、目で見てロマンを感じてみてくださいね(^^)
9月5日 【琉球のサムレー(士族)と日本の士族】
第一回目のイガルー・シマ文化財教室で、受講生から受けた興味深い質問の紹介をもう少し(^^)
同じ方から2つの質問があり、その内容がこのようなものでした。
・「士農分離」とありますが、琉球では「工」と「商」はどういう扱いだったのですか?
・沖縄では「うちは士族の出」と自慢する人がたいへん多くて驚きますが、士族は家譜への記載で増える仕組みだからとのこと。これは薩摩流ですか?薩摩もとても士族が多いですが。
確かに、「屋取」を学んでいると疑問に思うことですね(^^)
まず1つ目ですが、琉球国での身分制は日本の制度とは違い「士(サムレー)」か「百姓」かのどちらかしかありませんでした。職人や商人も町百姓と呼ばれ百姓扱いでした。ただし町百姓は農地を持たないので貢租負担の義務はなかったようです。(参照:高等学校 琉球・沖縄史)
2つ目については、いわゆる日本の「士族」は“武士”を祖先に持つ家系であり、華族家格(旧公卿・大名身分の家系)とは異なります。薩摩藩は雄藩でしたので武士の子孫(士族)が多いことは考えられるかと思います。一方、琉球の「士族(サムレー)」はどちらかというと日本の華族家格に近く、基本的に王子家、按司家の家系など、また首里王府にて功績を上げた者の家系が士族家格となりました。ただし増え続ける士族数に対し就ける職が限られていたため、無禄であったり田舎下りをする貧しい士族も数多くいました。それでも先祖崇拝性の強い沖縄だからこそ、士族のプライドを持つ家系も多いのではないでしょうか。(索引:広辞苑「士族」 参照:沖縄大百科事典)

(写真:那覇市歴史博物館 提供)
このような状況を鑑みても、琉球と日本はそもそも違う国だったということが改めて分かりますよね(^^)
さ~!第二回イガルー・シマ文化財教室は今度の土曜日(9月7日)に開催です!
9月4日 【古を学ぼう!「宜野湾歴史の道 文化財教室」開催決定!】
先日お伝えした通り、来月の10月19日より「宜野湾歴史の道文化財教室」がスタートします!

宜野湾市文化課では、宜野湾に残る古来よりの「歴史の道および関連文化財」を発掘・整備し、それらを国指定の文化財に登録できるよう日々奮闘しています。
そこで、市民の皆さん、県民の皆さんにもぜひ宜野湾にはかつてこのような道が通っていたこと、その一部が今でも残っていること、重要な史跡がいくつも発見されていることなどを知ってもらい、感動をともにしたい!

また、そこから思い浮かべることができる古の人々の生活模様、生活の知恵、現代にも受け継がれている伝統文化などもともに学びたい!
そのような背景をもとに、このたび「宜野湾歴史の道文化財教室」を開くことになりました。

特に米軍基地の返還跡地である西普天間住宅地区は、戦前までの地形や史跡、風景、道筋が僅かに残り、昔の人々の生活を今に知ることができるとても貴重なエリアとなっています。しかしこのエリアですら新しい街づくりで日々変貌を重ねていっています。
だからこそ、なるべく多くの方にオリジナルウチナーの地形・史跡・風景・道を今こそ目に焼き付けて欲しい。そして今後どのように残していけるのかをともに考えてほしいと思っています。
たくさんの方々のご参加をお待ちしております(^^)!
9月10日より応募受付開始です。
参加ご希望の方は、宜野湾市文化課までお電話かメールでお問い合わせください。
9月3日 【宜野湾市民図書館に「ごーやん先生」大増殖!ライバル出現に焦りか!?】
毎週火曜日は宜野湾市民図書館休館日ですが、明日以降ぜひ市民図書館を訪れてみてください(^^)
なんと!2週間の期間限定ではありますが、今話題の癒し系ロボット「LAVOT」が館内で皆さんの来館をお待ちしていますよ♪

“LOVOT[らぼっと]は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。”
実際目にしてきましたが、たしかにこれは、、カワ(・∀・)イイ!! (眠っている姿しか写真撮れなかったけど;;)
デジタルではあるんだけど、つぶらな瞳でまるで感情を持ったようなしぐさ。
このようなロボットがどんどん進化を遂げて、AI学習を取り込みながら人間同士と遜色のない会話や行動をする日も近いのかもしれないですね。
と、今回図書館を訪れたのはLAVOTを見る目的ではなく(少しはあった??)、来月からこちらの市民図書館2階でスタートする「宜野湾歴史の道文化財講座」のパネル展準備のためだったんです♪

現在進行形で、こちらのブログやSNSでも日々お伝えしている「宜野湾歴史の道」。
宜野湾市文化課では、宜野湾歴史の道の「国指定文化財登録」を目指して日々奮闘しています!
その内容や業務の模様、なぜ国指定を目指すのかなどなどをもっと市民県民に知ってもらいたい、一緒になって気運を盛り上げていってもらいたい!との想いで歴史の道文化財講座を開催させてもらう運びになりました(^^)
そして少しでも講座に関心を持ってもらえるように、興味をひいてもらえるように、図書館にて歴史の道に関するパネル展を開かせてもらえることになったというわけです。
ぜひ事前にパネル展にて歴史の道についての前情報を得て、興味が湧きましたら講座へのご参加もお待ちしております。どなたでも受講大歓迎です(^^)
受付開始は9月10日からとなっており、講座の詳細は明日にでも改めてアップしますね♪ 入り口にパンフレットも設置しています。

ところで図書館でパネル展をご覧になる際、少し驚きがあるかと思います(^^; 実はパネル片面のみでの講座紹介予定が、両面使ってもいいよとのご厚意で。取り急ぎ何かでスペースを埋めよう!と思い立ったのが、我らが文化課公式キャラクター「ごーやん先生」大集合!

いまだ「ごーやん先生」についての詳しいキャラ紹介が出来てないのが気がかりではありますが、今後ちょくちょく出現してくると思いますので、ぜひごひいきに~(^^)
ということで、ごーやん先生が大増殖したのは図書館に現れたLAVOTへのライバル心ではなく、急遽スペースを埋めるためと見た目インパクト重視のためでした~(^^) びっくりしないでね(^^;

こちらもぜひご覧になって、ごーやん先生を広めてもらえると嬉しいです♪
9月2日 【なぜ宜野湾市長田に米須さんが多い??】
早くも9月に突入しましたね~!夏が通り過ぎていく(;;)
でも沖縄サマーはまだなんとか粘れる!残暑を楽しむざんしょー!
ということで、(どういうこと?)先月に引き続き9月も第1週目の土曜日には、宜野湾市教育委員会主催の文化財教室「イガルー・シマ文化財教室」が開催されますよ♪
今年度のテーマは「屋取」(屋取についての詳細は過去ネタ7月19日を参照)
宜野湾市にも、屋取集落から発展して現在に至るエリアがたくさんあります。
前回の講座では、屋取とは何か?なぜ屋取が起きたのか?屋取の特徴は?などを那覇市歴史博物館の鈴木悠先生にお話ししていただきました。

(屋取イメージ図 沖縄県公文書館所蔵)
皆さん真剣に聞き入っており講座後の質疑応答でも質問が絶えず、時間の関係上間に合わなかった質問を用紙に書いて提出してもらいました。すると興味深い質問が数多く見受けられたので、こちらでもいくつか紹介してみたいと思います。
- 質問:長田区にはなぜ米須姓が多いのか。
宜野湾の方なら、うんうんと頷かれるかと思いますが、本当に長田-愛知区あたりは特に米須さんが多いんですよね。なんでって言われてもなんで?っていう感じですが(^^; 実は今回学んでいる「屋取」が大いに関係していたんです。
細かく全部書くとだいぶ長々となってしまうので、簡潔に
首里士族であった欽氏・米須一族<側系統>(元祖・欽創諸古波倉清愛)の四世清安は、勢高富勢頭に任ぜられ王城の防衛を務めました。その後、摩文仁間切米須の脇地頭に任ぜられ、米須親雲上となりました。以後米須姓を名乗るようになったといいます。五世の清和のころ(17世紀)に首里久場川から中城へ移り住み、その後長田へと分家しました。ウフヤーを「側ヌ前米須」といい、現在は宜野湾市長田で十一代目の方が継いでいおり(2004年時点)、長田では最も多い一族となっています。清安の次男と三男はそれぞれ「東リ米須」、「下ヌ米須」に分家し、その子孫が現在の中城村北上原と登又に広がっているとのことです。ちなみに清安の兄・清豊は尚豊王の宮廷画家として有名な自了(城間清豊)です。清豊が若くして亡くなったため清安が家督を継ぎました。(参照:中城村の屋取 ぎのわんの地名)
なるほど!これで米須さん in 長田の謎が解けましたね(^^)
白沢之図などで有名な自了もこちらの一族だったんですね~!
*白沢之図(那覇地域MPA中学校版)
このように歴史を紐解いていくと、ところどころで「あ!」という自分なりの発見があり、それがひとつひとつ結び付いていく感覚がたまらない高揚感を生み出すんですよね♪
さぁ、今月はどんなお話が聞けるのか!当日参加も可能ではありますが、駐車場に限りがありますので、なるべく公共機関をご利用になってお越しいただければと思います(^^)

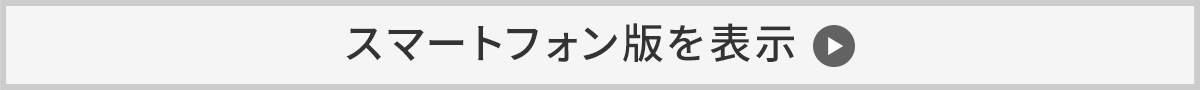






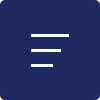
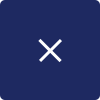

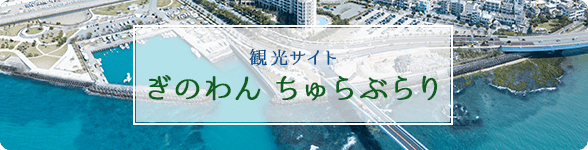


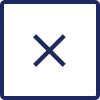









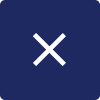























更新日:2024年10月01日